
たまたま買った株が10倍になったり、プロの投資家が失敗した事例を聞いたりすると、正直「株の勉強なんて意味ない」と考えがちです。
しかし、継続的に利益を狙うために、株の勉強は欠かせません。株について理解が進むと自分の目的にあった投資ができたり、根拠をもって利益を狙えたりとメリットが多いです。
本記事では、株の勉強が必要な理由やおすすめの勉強方法について解説します。長期的に株で利益を狙いたい方は、自分にあった勉強法を見つけるための参考にしてみてください。
株の勉強は意味ないと誤解される5つの理由

株の勉強は意味ないと誤解されるおもな理由は、以下の5つです。
- ギャンブルと捉えているから
- 短期的な利益を求めているから
- 情報の正確さを判断できないから
- 知識を実践に結びつけられないから
- 失敗談にマイナスイメージを持っているから
株の勉強に対する誤解が解ければ、知識をつけながら利益を狙えるようになるでしょう。勉強で得られるメリットを知りたいときは、こちらの章からご覧ください。
ギャンブルと捉えているから
株をギャンブルと捉えていると、勉強がおろそかになるでしょう。運要素が強く、勉強は必要ないと考えてしまうからです。しかし実際のところ、株の値動きには以下の要素が関係しています。
何も考えず「根拠のない勘」で株を売買すると、利益を狙いにくいです。株価の変動には必ず理由があるため、知識をつければ値動きの根拠を掴みやすくなります。
短期的な利益を求めているから
「すぐに儲けたい」という気持ちが強すぎると、株の勉強は無意味に感じるかもしれません。学んだ知識を活かす前に、我慢できず売ってしまうケースが多いからです。
たとえば、長期で利益が見込める株を「数日〜数週間」で売ってしまうと、1年後に株価が回復したときの利益を逃してしまいます。
知識をもとに根拠を持って「将来的に上がる」と考えるようになれば、短期的な値下がりを受け入れ、長期的なな視点を持てるようになるでしょう。
情報の正確さを判断できないから
情報の正確さを判断できないと、株の勉強に意味を感じられません。
ネットや書籍など投資に関する情報源はさまざまで、なかには間違いや詐欺につながるものも多いです。結果、何を参考にすべきかわからなくなる方もいるでしょう。
これまでも投資に関する詐欺被害がいくつも報告されており、金融庁も注意を促しています。
正確な情報で投資判断をするためにも、おもに金融庁や財務省などの公的機関を参考に勉強するのがおすすめです。
知識を実践に結びつけられないから
学んだ知識を実際の投資に活かせていない方も多いです。
勉強すると満足感を得やすいですが、株の購入や銘柄分析などで実践しなければ、経験や判断力が身につきません。
勉強を続けつつ、少額ずつ株を運用することで知識を活かせるようになります。
失敗談にマイナスイメージを持っているから
株の勉強に意味を感じない方は、他人の失敗談から影響を受けている可能性があります。
大きな失敗をした話は、印象に残りやすいからです。たとえば、身近な人が株で失敗していると「自分も投資で大きな失敗をするかも」といった不安な気持ちになります。
しかし、失敗の背景には「損失が怖くて冷静に判断できない」や「ネットの情報に流されてしまう」といった明確な原因があるケースがほとんどです。
正しい知識を身につけると株のマイナスイメージを解消でき、前向きに勉強を始められるでしょう。
株の勉強で得られる4つのメリット

株の勉強で得られるメリットは、以下の4つです。
投資に関する知識を身につければ、初心者からでも株で利益を狙えるようになるでしょう。
自分の目的にあった投資ができる
株の勉強をすれば、自分の目的にあった投資ができます。
ライフプランやリスク許容度に合わせて、柔軟に投資スタイルを選べるからです。
仮に「老後資金の確保」が目的であれば、NISAやiDeCoなどの長期運用向けの戦略を学ぶことで、正しくゴールに向かって投資を続けられます。
また、短期で利益を狙う場合、値動きの大きい個別株やテーマ株などでハイリスクハイリターンな投資をするのも戦略のひとつです。
知識を幅広く身につけ、目的にあった投資スタイルを確立しましょう。
根拠を持って利益を狙えるようになる
根拠を持って利益を狙うために、株の勉強は欠かせません。
たとえば、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)などの財務指標からは、企業の株が割安か、利益が出ているかを客観的に判断できます。
また、株式投資に関する情報は市場にあふれており、勘で実践すると成果は得にくいです。
基礎知識と分析力を身につければ、利益が見込める株を適切なタイミングで売買できるようになるでしょう。
株で利益を狙うための指標について知りたい方は、こちらの「株式投資に役立つ指標とは|明日から使える数値をわかりやすく解説!」記事を参考にしてみてください。
含み損が出ても冷静な判断で損失を抑えられる
株の勉強をすると、含み損が出たときでも冷静な判断で損失を抑えられます。
例を挙げると、株価の急落に不安を感じて売却した場合、将来的に回復した際の利益を逃す可能性があります。
しかし、売るタイミングを学んで「〇%の値下がりで損切りする」や「〇円になったら利益確定する」といった基準を決めることで冷静に判断できるでしょう。
勉強を通じて論理的な判断ができると、含み損が出た場面でも落ち着いて対応できるようになります。
損切りラインの決め方については、こちらの「【塩漬け株に悩む方】株の損切りができない本当の理由と損切りラインの見極めポイントを実例をまじえて解説」記事で解説しています。
世界中の政治や経済の知見が深まる
株価は世界情勢によっても変動するため、値動きを読み取るには「政治」や「経済」について学ぶ必要があります。
各国の動きや政策などを理解すると、利益が見込める投資先や売買時期などを予測しやすくなるでしょう。
また、政治の知識を身につけることで、ニュースや世界情勢への理解が深まるというメリットもあります。
「世界の出来事」と「自分の生活」のつながりを実感できるようになれば、より広い視野で物事を考えられるようになるでしょう。
株の勉強を効率よく進める4つのステップ

株の勉強を効率よく進めるためには、以下の4つのステップで行動するのがおすすめです。
株の勉強を進めると知識と経験が身につき、的確なタイミングで売買できるでしょう。
1.最低限の基礎知識を学ぶ
株を長く運用し続けるために、最低限の基礎知識を身につけておきましょう。とくに、初心者は以下のようなリスク管理について学ぶべきです。
- 暴落時の対処法
- 株価が変動する要因
- リスクとリターンの関係性
- 余剰資金で投資することの重要性
リスクを考えずに多額の株を買ってしまうと、損失で生活に支障が出る可能性があります。まずは基礎知識をおさえ、株で損をしないように対策しましょう。
2.少額で株を買ってみる
最低限の知識が身についたら、少額で株を買ってみましょう。実践しないと、知識を利益に繋げられないからです。
実際に買った株で利益が出ると、勉強を続けるモチベーションにもつながります。
また、学んだ分析方法を試したり期待値の高い企業の株を買ったりすることで、実践的なスキルも身につくはずです。
3.運用中の株について勉強する
保有している株の理解が深まると、売買時期を判断しやすくなります。とくに見るべき項目は、以下のとおりです。
- 企業の業績
- 企業の期待値
- 配当金の有無
- 株主優待の有無
運用中の株について勉強すれば知識を反映しやすいので、利益にもモチベーションにもつながります。
4.勉強の範囲を広げながら投資を続ける
勉強と実践を繰り返せるようになったら、徐々に学びの範囲を広げましょう。
ほかの銘柄や幅広い投資戦略を学ぶことで、効率よく利益を狙えるようになります。
具体的には、以下について勉強するのがおすすめです。
- 株式以外の投資先(例:投資信託、債券、不動産など)
- 保有銘柄に関する業界の将来性(例:商社、製鉄、運送など)
- ニュースやネットで話題になっている銘柄の詳細(例:株価、配当金、業績など)
市場にあわせて柔軟な資産運用を続けるためにも、範囲を広げながら投資の勉強を続けてみてください。
株の初心者におすすめの勉強法

株の初心者が勉強を始めるなら、以下の媒体を活用するのがおすすめです。
- 経済新聞
- 書籍、雑誌
- 証券会社や銀行のコラム
- 株のシミュレーションアプリ
とくに、経済新聞や大手出版社の書籍などは会社の編集・監修を通して発信されているケースが多く、情報の信頼性も高いです。
SNSやYouTubeなどのメディアで学ぶのも良いですが、情報が間違っている可能性もあるため、信頼性の高い情報とあわせて理解を深めましょう。
おすすめの勉強法については、こちらの「株式投資の勉強法 おすすめ5選|初心者向け株の基本、注意点などをわかりやすく解説」記事で詳しく解説しています。
株の勉強をするときに意識すべき2つのポイント

株の勉強をするときに意識すべき2つのポイントは、以下のとおりです。
株について正しい理解を深め、実践に役立つ勉強を続けましょう。
情報を鵜呑みにしない
株の勉強で得た情報をそのまま信じるのではなく、自分で裏付けをとる姿勢をもちましょう。
情報を鵜呑みにして投資すると、大きな損失につながる可能性があるからです。
たとえば「A社の株価が必ず上がる」といった情報を信じて多額の株を買ったものの、実際には下落して資産を失うケースもあります。
企業のIR資料や信頼できるメディアなど、複数の情報源をチェックしてデータの正確さを検証すべきです。
始めやすく続けやすい勉強法を選ぶ
大きな負担を感じると、株の勉強は長続きしません。難しい専門書や複雑な分析から始めるのではなく、自分の知識レベルや生活スタイルにあった方法で学ぶのがおすすめです。
たとえば、以下の勉強法なら初心者でも始めやすく続けやすいでしょう。
- 雑誌の特集記事を読んで参考にする
- 通勤中にスマホで経済ニュースを読む
- SNSやYouTubeなどを参考程度に視聴する
- アプリで投資結果をシミュレーションしてみる
- 証券会社の初心者向けコラムや動画を活用して学ぶ
手軽な勉強法で習慣的に勉強を続けてみてください。
株の勉強はしたけれども実際に投資をしてみたら難しかった。とくに売る時に迷ってしまい売り時を逃してしまったという方が多くいらっしゃいます。利益を確保するのは大事ですが時には損切も必要になり、これができないと株で資産形成は難しくなります。しかし自分ではできないという方には、投資顧問の利用をおすすめします。当サイトを運営するライジングブル投資顧問は、株の「売買サポート」を行っております。ライジングブルの売買サポートサービスは、3ヶ月9,000円で買い推奨だけではなく、売却、銘柄入替するところまで、リスク管理をしながらサポートします。
個人の方には難しい売り推奨のアドバイス実績も豊富にあり、
・これから株をはじめる方
・株をやっているが資産が一向に増えない方
・損切ができず株を塩漬けにしがちの方
・損切ができない方
には、ライジングブルの売買サポートをおすすめします。
18年の歴史と3万人以上サポートしてきた実績で、少額資金ではじめても成功できるよう株の売買をサポートします
まとめ

株で利益を狙うためには、コツコツ勉強を続ける必要があります。知識が身につくと根拠を持って投資できるようになり、暴落時にも冷静な判断ができるでしょう。
それでも「何から始めたらいいかわからない」という方は、以下の流れで株の勉強を進めてみてください。
- 最低限の基礎知識を学ぶ
- 少額で株を買ってみる
- 運用中の株について勉強する
- 勉強の範囲を広げながら投資を続ける
ただし、ネットや他人からの情報には間違ったものもあります。
公的機関や複数の情報源を参考にしつつ、余剰資金で少額から投資に挑戦してみてください。

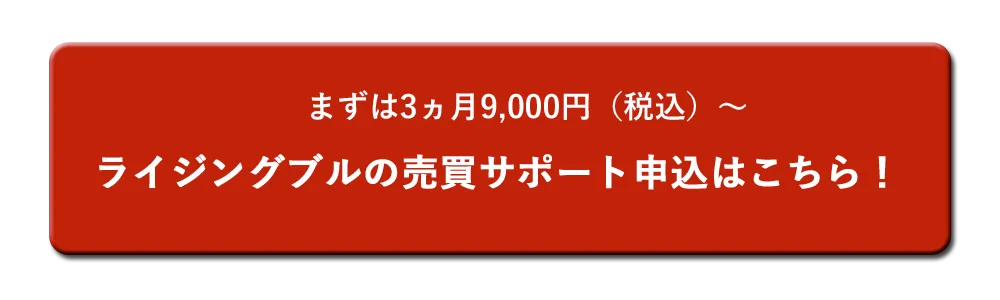

コメントComment