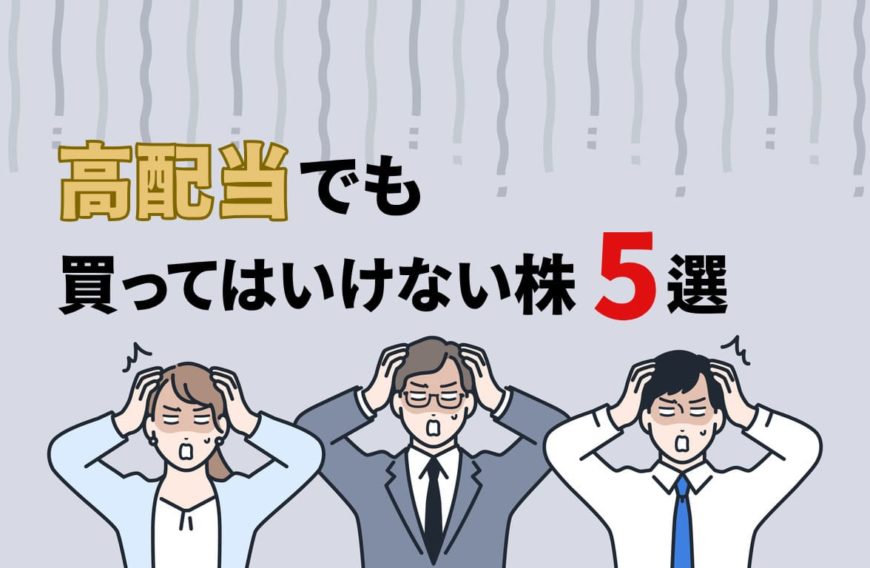
不労所得として魅力的な配当金。
「生活に金銭的なゆとりを持ちたい」や「将来的にはFIREしたい」といった願望から、高配当株への投資を検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、投資先の企業が過去に高い配当金を出していても、将来的に高配当が続くとは限りません。
本記事では、高配当株で人気でも2025年に買うべきではない、買う際には注意を必要とする5銘柄について、なぜ買ってはいけないのか理由を紹介します。
高配当株投資で失敗しないための参考にしてみてください。
目次
1.マツダ|北米依存の利益率により今後の業績が不透明

マツダ(東証プライム:7261)は自動車やトラックの製造・販売をしている日本の自動車メーカーです。
ロータリーエンジン開発といった独自技術が強みで、生産拠点は日本、販売拠点は北米を中心としています。
直近の配当情報とは、以下のとおりです。
| 事業年度 | 年間配当金 | 配当利回り | 配当性向 |
| 2026年3月期(予想) | 未定 | ー | ー |
| 2025年3月期 | 55円 | 4.41% | 30.4% |
| 2024年3月期 | 60円 | 3.96% | 18.2% |
| 2023年3月期 | 45円 | 4.16% | 19.8% |
※みんかぶ|マツダ (7261)(2025年7月16日時点の情報)
現在のマツダ株は、※PER(株価収益率)4.80倍、※PBR(株価純資産倍率)0.30倍と、数字上は割安に見えます。2025年3月期は年間配当は55円、配当利回り4.41%と一見、高配当株に見えますが、あくまで上記は「過去の実績」をベースにした数値です。
※PERは株価が1株当たりの純利益の何倍になっているかを示します。株価が「1年間の利益」の何倍の値段になっているかを示す指標で、PERは低いほど「利益に対して割安」、高いほど「利益に対して割高」と判断されます。
また、PBRは、株価が「会社の正味の財産(純資産)」の何倍の値段になっているかを示す指標です。PBRが1倍未満だと理論上は「解散価値より安い」ことになります。どちらも株が「高いか安いか」を判断する目安として使われる指標です。

マツダは海外事業が多いために世界情勢の影響を受けやすく、前期と同水準の配当金が出せるかはわかりません。ここからは、マツダ株の配当金に関する3つのリスク要因について解説します。
リスク要因1|アメリカ関税政策による悪影響を受けやすい
マツダは北米での販売台数が多く、トランプ政権による関税政策の影響を受けやすいです。そもそも、関税は輸入品にのみ課されるため、現地生産した自動車は対象外となります。
ほかの大手国内メーカーが70〜80%程度を現地で生産しているなか、マツダの現地(アメリカ国内)生産比率は約50%程度です。
つまり、マツダは販売台数の半数において、トランプ政権の「15%関税上乗せ」に影響されることになります。
北米での売上が全体の約45%を占めるマツダにとって、関税コストが増加すると配当原資を確保しにくくなるでしょう。
リスク要因2|利益率がさらに悪化する可能性がある
2025年3月期において、マツダは前年度より業績が悪化(営業利益26%減、純利益45%減)しています。
おもな原因は、運送費や材料費、販売促進費(販売台数を増やすための施策に利用する資金)の増加によるものです。
また、シェア率の高い北米での売上を守るために販売奨励金を増やしたり、販売価格を据え置いたりする必要があります。
上記の費用をマツダが負担すると、利益率はさらに下がるでしょう。
さらに、トランプ関税の影響で利益が減ることも懸念されるため、将来的には配当金が減る可能性があります。
リスク要因3|2026年3月期の配当予想が出ていない
2025年6月時点で、2026年3月期のマツダの配当予想は未定です。今後の業績について、不確定な要素が多いからだと考えられます。
マツダの業績が悪化するおもなリスク要因としては、以下が挙げられます。
- 価格競争の激化
- 為替変動の影響
- アメリカの関税政策
- 製造・販売コストの上昇
上記の見通しが立たないため、2026年3月期は業績予想も未定です。業績の見通しが立つと配当の予想が出やすくなるため、マツダ株に投資する際は、四半期ごとの決算短信で業績や配当の予想が出ているかチェックしましょう。
2025年8月20日追記
日米関税交渉で、相互関税の10%の基本税率が8月1日から15%へと引き上げられる内容で合意されました。事前通告の相互関税25%は回避された。乗用車への適用が25%→12.5%(従前の2.5%を併せると15%)に半減されたことにより、当初の想定より影響が軽減される期待から株価が反発しています。ただし、円高の進行や依然として残る関税の影響の懸念も残ります。また、関税が完全に撤廃されたわけではないため、手放しには喜べる状態ではないと思います。
(参考:MAZDA 企業サイト|株主還元、2025年3月決算短信、プレゼンテーション資料)
2.日本製鉄|製鉄業は他業種の業績に振り回されやすい

日本製鉄(東証プライム:5401)は日本の三大製鉄メーカーのひとつで、鉄鋼業界でも業績がトップクラスの企業です。15カ国以上に拠点があり、世界中で鉄の製造を中心とした事業を展開しています。
直近の配当情報を下表にまとめました。
| 決算期 | 年間配当金 | 配当利回り | 配当性向 |
| 2026/3(予想) | 120円 | 4.33% | 62.8% |
| 2025/3 | 160円 | 4.91% | 45.6% |
| 2024/3 | 160円 | 4.88% | 26.8% |
| 2023/3 | 180円 | 7.83% | 23.9% |
※みんかぶ|日本製鉄 (5401)(2025年7月16日時点の情報)
現在の日本製鉄株は、PER(株価収益率)8.13倍、PBR(株価純資産倍率)0.56倍と、一見すると割安に見えます。また、配当利回り4%超えの優良な高配当株に見えますが、上記はあくまで過去の実績です。
2026年3月期の予想では、配当利回りが減少しているうえに、PERでも割高感が出始めています。
本章では、日本製鉄株のリスク要因を3つ解説します。
リスク要因1|アメリカ関税政策の間接的なダメージを受けやすい
日本製鉄の米国向け輸出は1.5%と少量であるため、直接的な影響は限定的であると思われます。しかし、問題は間接的な波及効果にあるとされています。
鉄鋼は自動車や機械などの完成品に使われる基幹素材であり、それらの完成品が米国で売れなくなれば、日本国内での生産が減少し、日本製鉄の納入量も減る構造です。
さらに、米国需要を失った中国や韓国の鉄鋼材が東アジアに流入し、価格下落圧力を加速させる「負の連鎖」が起こりかねないと指摘されています。
1.アメリカが日本からの輸入車に高い関税をかける
↓
2.国内自動車メーカーがアメリカの現地生産に移行する
↓
3.国内での自動車生産が頭打ち状態となる
↓
4.自動車用鉄鋼素材の国内需要が縮小する
↓
5.日本製鉄の売上・利益が減少する
↓
6.米国需要を失った中国や韓国の鉄鋼材が東アジアに流入するため価格下落圧力が加速
もう1つ、日本製鉄のマージンは100ドル/トンという過去10年の平均を100ドル以上も下回る極めて低い水準で推移しており、これはアジア市場の悪化が背景にあります。米国や欧州市場も不安定でグローバルな需給バランスが崩れており、これまでのような安定利益の確保が困難な局面を迎えています。
そのため、関税の直接的な対象ではありません。しかし、以下の流れでトランプ関税の影響が広がると、日本製鉄も間接的にダメージを受ける可能性があります。
リスク要因2|当初の予想より配当額が減る可能性がある
日本製鉄は、2026年3月期の会社想定EPS(一株当たり利益)が191円となり、前期(2025年3月期)の350円から約30%の減益となると予想しています。
同社は、2012年以降「配当性向30%」を維持する安定した配当政策を掲げており、2026年3月期もこの方針を維持すると述べています。しかし、2026年3月期の日本製鉄の配当金は、年間配当は約120円の予想で前期の年間160円から40円減配となる見込みです。
この数値でも、一見高配当に見えますが、現在の株価指標が2025年3月期ベースのものであり、将来の減益が織り込まれていない可能性があるためで、実際には予想よりもさらに減る可能性があります。
なぜなら、2025年3月決算時点で発表された業績予想は、関税や為替の影響を考慮していないからです。前述のとおり、日本製鉄にもトランプ関税による間接的なダメージが予想されます。
2026年第1四半期決算で業績予想が大きく下方修正された場合、配当も減額される可能性があります。
次回の決算短信を見て業績の改善が確認できるまでは、投資を控えるのが無難です。
リスク要因3|USスチール買収に伴う高リスクと国内自動車セクターの需要縮小
2025年6月18日、日本製鉄はUSスチールの買収を正式に完了しました。これにより、USスチールは日本製鉄の完全子会社となりました。
それにより、米国市場での事業拡大と成長機会や米国の関税障壁の回避等も期待されております。しかし、米国政府による経営への統制強化や2028年までに約110億ドル(1兆5000億円超)規模の追加投資など多大なリスクが残ります。
このような大型資金が必要な状況では、一時的な還元余力は減少し、臨時配当は期待薄であり、今後数年は再投資に徹するフェーズだと見られています。加えて、売上の約3割を占める自動車セクターでは、北米向け輸出の停滞、EV化による車体構造の変化、価格競争の激化が重なり、日本国内の自動車生産は頭打ち状態にあります。
完成車メーカーの現地生産シフトが進む中で、日本製鉄の国内需要は縮小傾向にあり、これも収益の不安定さにつながるリスク要因です。
(参考:2025年3月期決算短信、日本製鉄2024年度決算説明会)
3.伊藤ハム|大幅な増配は記念配当による一時的なもの

伊藤ハム米久ホールディングス(東証プライム:2296)は加工食品や冷凍食品などを製造・販売している日本の食品メーカーです。
直近の配当情報を、以下の表にまとめました。
| 決算期 | 年間配当金 | 配当利回り | 配当性向 |
| 2026/3(予想) | 320円 | 6.40% | 103.7% |
| 2025/3 | 145円 | 3.65% | 62.8% |
| 2024/3 | 125円 | 3.22% | 45.7% |
| 2023/3 | 120円 | 3.27% | 40.8% |
※みんかぶ|伊藤ハム米久ホールディングス (2296)(2025年7月16日時点の情報)
現在の伊藤ハム株は、PER(株価収益率)21.63倍、PBR(株価純資産倍率)1倍でPERは業界平均(食品業界のPERは15~20倍程度)と比較してやや高めな印象です。2026年3月期に「記念配当」が実施されるため、配当利回りや配当性向が大幅にアップしています。
しかし、今期の高い配当金は一時的なものです。本章では、伊藤ハム株のリスク要因を3つ解説します。
リスク要因1|大幅な増配は一時的な記念配当の影響が大きい
2026年3月期の予想では、伊藤ハムの配当金は前期より175円も増配しています。しかし、今期の増配は伊藤ハムと米久の経営統合10周年を祝う「記念配当」に過ぎません。
つまり、本来の配当は145円程度です。
記念配当を除いた145円ベースの配当利回りは約2.9%程度なので、過去の配当利回りを大きく下回ります。
長期的な配当収入を期待して投資する場合、2027年3月期以降に記念配当がなくなれば、想定よりも利回りが低くなるでしょう。
リスク要因2|業績予想はあくまで努力目標ベース
伊藤ハムは2026年3月期の業績を強気に予想していますが、あくまで努力目標です。
「連結純利益34%増、売上高4%増」という数値を達成できなければ、期待どおりの配当が実現できない可能性があります。
また、業績が未達の場合、PERが上昇し割高と判断されて売却と買い控えが進み、株価が下がる可能性が高いです。
長期運用を検討する際には四半期決算ごとに業績をチェックし、予想から大きくずれているときは投資戦略を見直しましょう。
リスク要因3|食料品の消費税ゼロ構想に振り回される可能性
立憲民主党が掲げる「食料品の消費税ゼロ構想」は、食料品にかかる消費税を廃止し、家計負担を減らす政策です。
国内の食品メーカー最大手の伊藤ハムは、構想の実現可否に影響を受ける可能性があります。
構想が実現すれば消費者が食品を買いやすくなるため、売上・利益の大幅増が期待できます。しかし、日本政府は税収確保を重視しており、減税には慎重な姿勢です。
石破首相も消費税減税には否定的で、構想が実現する可能性は低いと考えられます。
現状では、政策の不確実性に左右される投資よりも、安定した配当を期待できるほかの銘柄を検討する方が無難です。
(参考:伊藤ハム米久ホールディングス025年3月期決算短信、2024年度通期(4-3月)決算説明資料)
4.商船三井|海運市況の変動で配当継続に不透明感
商船三井(東証プライム:9104)は日本の大手海運会社で、世界最大級の船隊を保有する総合海運グループです。140年以上の歴史を持ち、鉄鉱石や石炭などの資源輸送、原油やLNGなどのエネルギー輸送、自動車輸送、コンテナ船事業など、多岐にわたる事業を展開しています。
直近の配当情報を、以下の表にまとめました。
| 決算期 | 年間配当金 | 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/3(予想) | 150円 | 3.17% | 30.5% |
| 2025/3 | 360円 | 6.4% | 30.3% |
| 2024/3 | 220円 | 3.7% | 30.4% |
| 2023/3 | 560円 | 10.5% | 25.4% |
※みんかぶ|商船三井 (9104)(2025年7月16日時点の情報)
現在の商船三井株は、PER(株価収益率)3.98倍、PBR(株価純資産倍率)0.63倍で数値的には割安な印象です。2026年3月期の年間配当金予想は150円で、2025年3月期360円から58%減配予定です。
本章では、商船三井株のリスク要因を3つ解説します。
リスク要因1|海運市況の調整局面で大幅減益懸念
2025年3月期は地政学リスク(紅海情勢など)による運賃高騰、港湾混雑による供給逼迫、円安の追い風といった一時的な要因で大幅増益となりました。
しかし、2026年3月期はコンテナ・自動車船市況のピークアウトや米関税による世界経済停滞で純利益60%減と予想されています。運賃低下が利益を直撃し、配当余力も縮小する見込みです。
リスク要因2|米国関税政策の影響
米国トランプ大統領の政策により対中関税が強化され、複数の中国製品に25~60%の追加関税が正式発動されました。これにより、アジア発の海上輸送に大きな影響が出ており、既に輸送量の減少傾向と運賃の軟化が確認されています。
また、商船三井は、コンテナ船、自動車船のいずれも北米向け輸送比率が非常に高く、この関税ショックが直撃する構図にあります。商船三井自身も関税負担で経常利益を約400億円押し下げる試算を示しています。
リスク要因3|中国経済の減速によるドライバルク事業への影響
商船三井のもう一つの収益柱であるドライバルク事業は、中国経済の影響を強く受けます。鉄鉱石や石炭、穀物などの荷動きは中国の内需に支えられてきましたが、現在中国は内需減速と不動産不況に直面しており、今後の輸送需要は伸び悩むと見られています。
これはコンテナ船事業ほど報道されていませんが、極めて重要なリスクであるとされています。
(参考:ロイター、OCEAN NETWORK EXPRESS開示資料 、商船三井 事業報告書)
5.SUBARU(スバル)|北米依存と品質・業績不確実性
株式会社SUBARU(東証プライム:7270)は、自動車、航空機、産業機器などを製造する大手メーカーです。1917年に中島飛行機研究所として創業し、その後、富士重工業を経て、2017年に現在の社名に変更されました。
直近の配当情報を、以下の表にまとめました。
| 決算期 | 年間配当金 | 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/3 | 115円 | 4.55% | - |
| 2025/3 | 115円 | 3.98% | 25.1% |
| 2024/3 | 106円 | 3.07% | 20.8% |
| 2023/3 | 76円 | 3.59% | 29.1% |
※みんかぶ|SUBARU (7270)(2025年7月16日時点の情報)
現在のスバルは、PER(株価収益率)5.50倍、PBR(株価純資産倍率)0.68倍、配当利回り4.55%と、数字上は割安に見えます。しかし、これは2025年3月期の実績をベースに算出されたものであり、今後の状況によっては「未定」とされている2026年3月期の業績が大幅に悪化し、配当維持が困難になる可能性が指摘されています。
本章では、スバル株のリスク要因を3つ解説します。
リスク要因1|北米市場依存による関税リスク
スバルは販売している車の約88%が海外販売であり、その中でも米国市場への依存度が約79%と圧倒的な比率を占めています。そのため、米国の関税引き上げが直撃リスクとなる可能性があります。通商交渉の結果次第でコスト増と価格競争力低下が避けられない状況となっています。
25%の関税が継続されれば、スバルの営業利益に最大25億ドル(約3,00億円)ものマイナス影響があると会社側は試算しています。これは業績の前提が根本から変わるレベルのインパクトです。実際に関税は15%になりましたが
リスク要因2|業績見通し未定で配当継続が不透明
2026年3月期連結業績見通しは「合理的な業績見通しを算定することが困難である」という理由から「未定」となっています。営業利益1,000億円レベルの確保を目標にするのみとなっています。業績と連動する配当政策の透明性がないため、投資判断が難しくなっています。
リスク要因3|利益を圧迫する販売インセンティブ増加とその他コスト要因
米国市場での販売維持のため、スバルは1台あたり1,200ドルもの販売奨励金(販促金)を投じており、これは前年から300ドルも増加しています。これにより、台数を維持しても利益が削られる構図にあり、営業利益を圧迫しています。
また、6月以降の北米での販売価格の値上げが販売の腰折れを招く可能性や、為替変動(円高リスク)、原材料費の高騰(鋼材、電池など)も原価率を悪化させ、今後数四半期にわたって利益を圧迫する可能性があります。
(参考:2025年3月期決算説明会(スクリプト付)、2025年3月期 年度決算 アナリスト向け説明会 主な質疑応答)
個別株への投資をしてみたいけれど株の売り買いの判断に迷って自分ではできないという方には、投資顧問の利用をおすすめします。当サイトを運営するライジングブル投資顧問は、株の「売買サポート」を行っております。ライジングブルの売買サポートサービスは、3ヶ月9,000円で銘柄の買い推奨だけではなく、売却、銘柄入替するところまで、リスク管理をしながらサポートします。
個人の方には難しい売り推奨のアドバイス実績も豊富にあり、
・これから株をはじめる方
・株をやっているが資産が一向に増えない方
・損切ができず株を塩漬けにしがちの方
・損切ができない方
には、ライジングブルの売買サポートをおすすめします。
18年の歴史と3万人以上サポートしてきた実績で、少額資金ではじめても成功できるよう株の売買をサポートします
まとめ

本記事では、2025年におすすめできない高配当株を5つ紹介しました。
たとえ過去の配当実績が良くても、今後も同じ水準の配当金がもらえるとは限りません。
そのため、いままで高配当株でも2025年は買うことをおすすめできない可能性のある株が実はあるのです。
高配当株投資を検討する際は、業績や配当予想だけでなく、関税政策などの外部環境や企業の財務体質についても確認し、また、業績の急変などがないか四半期ごとの決算短信でチェックするようにしましょう。
市場全体を可能な範囲でリサーチすれば、減配による損失リスクを最小限に抑えられるはずです。
銘柄選びの参考にしてみてください。

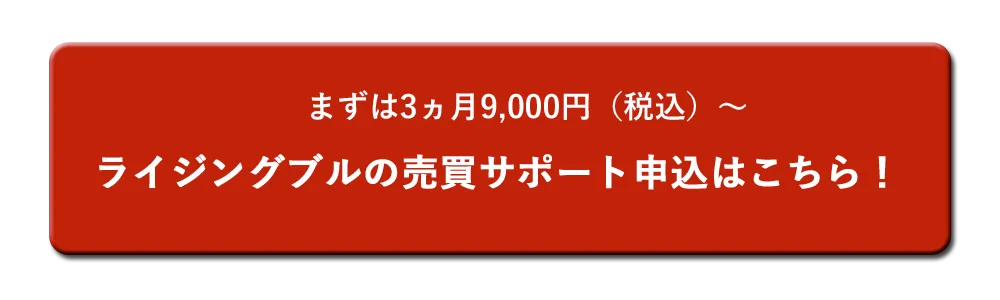
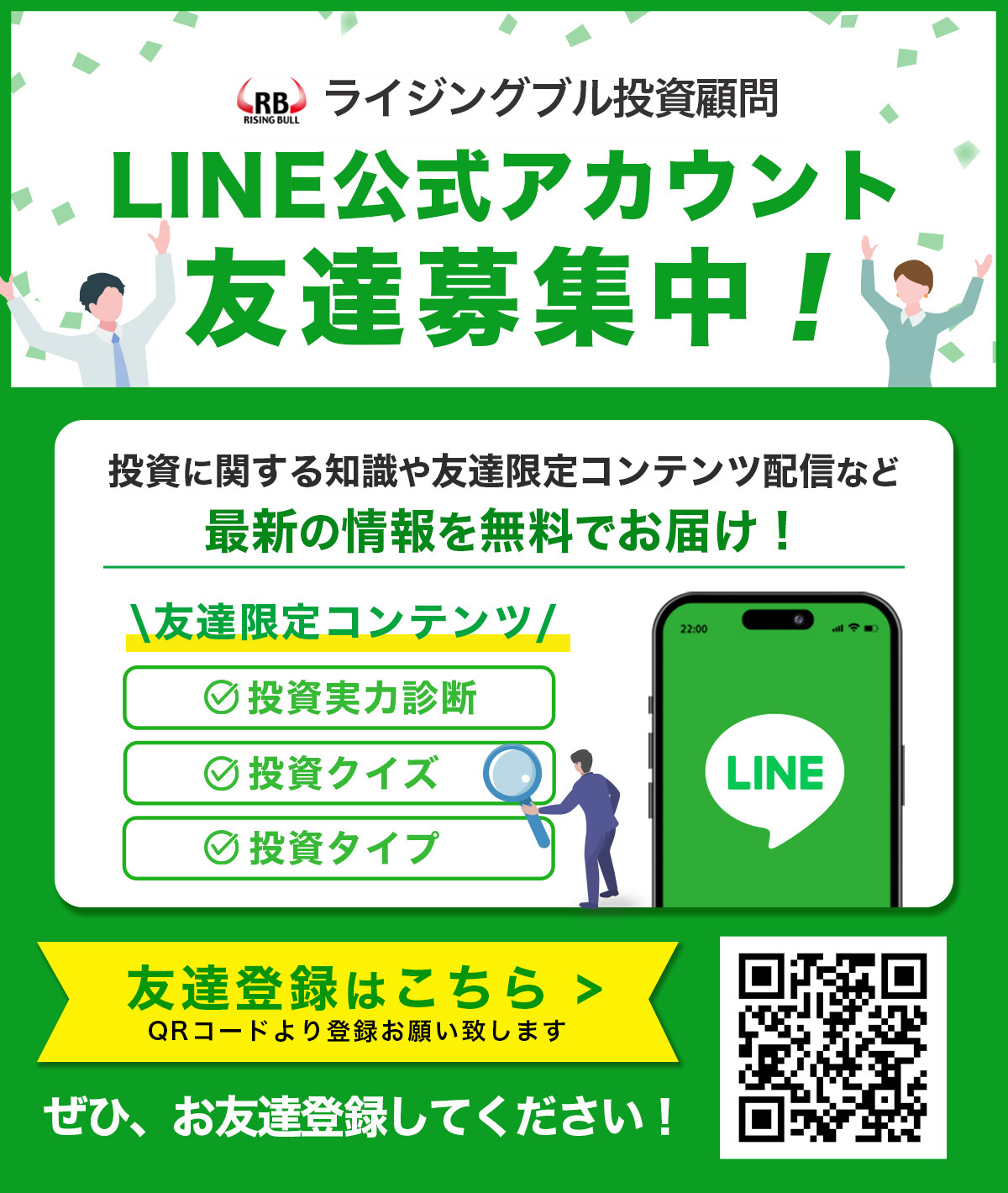
コメントComment