
NISAでの資産運用は、早めに始めて長期で続けていけば非課税メリットを最大限に受けられます。
「まずは始めてみよう」という気持ちでNISAを始めた方も多いと思いますが、運用が軌道に乗ると、将来的に資産をどう活用すべきか考えるタイミングが出てくるでしょう。
しかし、非課税期間が無期限となった新NISAでは、いつ、どのような方法で資産を引き出せばよいのか判断が難しいです。
そこで本記事では、新NISAの5つの出口戦略と具体的な取り崩しシミュレーションを紹介します。また、2023年までの一般NISAやつみたてNISAを利用している方向けの出口戦略についても解説します。
本記事を読めば、自分に合った資産の取り崩し方法をイメージできるので、計画的にNISAでの投資を続けられるようになるでしょう。
新NISAをこれから始めるという方はまずは「新NISA活用ガイド!初心者にわかりやすく新NISAの仕組みとメリットや活用事例を解説」をご覧ください。
目次
新NISAで出口戦略が重要な3つの理由

2024年にNISA制度が改正され、これまで以上に出口戦略について考える必要性がでてきました。主な理由は、以下の3つです。
- 買える商品が増えたから
- やめどきを自分で決める必要があるから
- 同じ元本でも受け取り方で利益が増減するから
それぞれ解説します。
買える商品が増えたから
新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠で資産を運用できます。旧NISAと比べて買える商品の数が増えたので、どの商品をいつ売るかがさらに複雑になりました。
とくに、成長投資枠には「値動きが大きい個別株」や「配当金を受け取れるETF」などの商品も含まれるので、売るタイミングの判断が難しいです。
前もって出口戦略を考えておけば、売るタイミングを冷静に判断できるので、必要な資金を確保できるようになるでしょう。
やめどきを自分で決める必要があるから
2023年までのNISA制度では、一般NISAで5年、つみたてNISAで20年という、非課税で運用できる期間が決まっていました。しかし、新NISAの非課税期間は無期限なので、自分でやめどきを決める必要があります。
また、長期的に運用を続けていると、値上がり益や配当益が発生しているかもしれません。「今後も運用を続ければ、もっと利益が出るかもしれない」と考えると、なかなか売る決断ができなくなるので、前もって出口戦略を考えておくべきでしょう。
同じ元本でも受け取り方で利益が増減するから
積み立てた資産を取り崩しても、NISA口座に残っている商品の運用は続きます。そのため、同じ元本でも「どの商品を」「いつ」「どのくらい」売却するかによって受け取れる利益が変わります。
たとえば、元本1,500万円を20年分の生活費にする場合、受け取り方法での金額の違いを以下の表にまとめました。
| 受け取り方法 | 受け取り額(毎月) |
| >一括 | 6.25万円 |
| 20年間かけて取り崩し(年間利回り:5%想定) | 約10万円 |
参考:みんかぶ (投資信託)|資産運用シミュレーション | 積み立てから取崩しまで
一括で受け取る場合と比べて、NISA口座内で運用しながら取り崩す方が、毎月約4万円も多く受け取れる計算です。
受け取り額や期間、保有する商品の種類によっても最終的な受取額が変わるので、より多くの資産を受け取れるように出口戦略を考えておく必要があります。
新NISAの5つの出口戦略
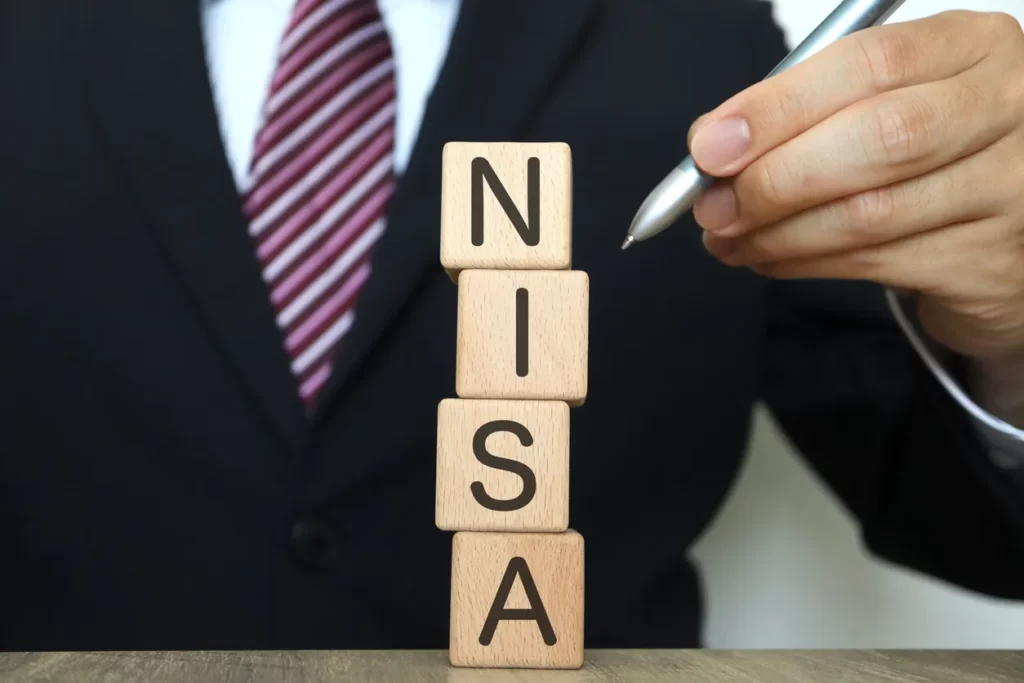
新NISAを有効的に活用するための出口戦略として、以下の5つが挙げられます。
- インカムゲイン戦略|個別株やETFの配当金を受け取る
- コア・サテライト戦略|低リスク資産の割合を増やす
- 4%ルール戦略|資産が減らないように取り崩す
- 中長期的な売買戦略|成長投資枠を再利用する
- 一括で現金化する戦略|すべての商品を売る
パターンを知っておけば、自分がどの戦略で老後資産を準備すべきかイメージできるようになるでしょう。
インカムゲイン戦略|個別株やETFの配当金を受け取る
インカムゲイン戦略は、成長投資枠で高配当の株やETFを買い、配当金を受け取って老後資金をまかなう出口戦略です。
配当金額が下がらなければ、たとえ株価が下がっていても、安定して生活資金を確保できる可能性があります。また、受け取った配当金で株を買い増せば、さらに効率よく資産を増やせるでしょう。
ただし、安定して配当金を受け取れる銘柄を見つけるのは、なかなか難しいです。加えて、配当金額が減ったときはポートフォリオの組み直しが必要になるので、企業や社会情勢に関する情報収集も欠かせません。
それでも、業績が安定している高配当株は、株の値動きが小さい傾向にあります。インカムゲイン戦略をうまく活用すれば、株価の上下に左右されにくい、安定的な老後資金の確保が期待できます。
コア・サテライト戦略|低リスク資産の割合を増やす
コア・サテライト戦略とは、 低リスクな「コア資産」とハイリスクハイリターンな「サテライト資産」に分けて資産を運用する方法です。それぞれの運用例を、以下の表にまとめました。
| 区分 | 投資商品の例 | 割合 |
| コア資産 | 現金、インデックスファンド | 70% |
| サテライト資産 | 個別株、ETF | 30% |
資産が必要になったときにサテライト資産から売却していけば、株価が大きく下がったタイミングでもコア資産で必要な資金を確保できます。
たとえば、オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)などのインデックスファンドは保有したままで、値上がりしている個別株から売却するといったケースも、コア・サテライト戦略のひとつです。
安定的に資産を確保しながら運用を続けられるので、お金の心配がない状態で効率的に資産を増やせるでしょう。
4%ルール戦略|資産が減らないように取り崩す
4%ルール戦略とは、NISA口座で積み立てた資産を毎年4%ずつ取り崩していく方法です。
1998年に行われたアメリカのトリニティ大学の研究により判明したルールで、4%ルールに従って資産を取り崩せば、30年以上経っても資産がなくなる確率は低いとされています。100年時代でも、将来的にお金が足りなくなるといった不安を減らせるでしょう。
ただし、実現には、年間に必要な支出の「25倍の元本」が必要なので、年間200万円の生活資金を確保するための必要元本は5,000万円です。
また、4%ルールはアメリカの株式の成長率(7%)から物価上昇率(3%)を引いて算出された数値なので、日本人にはうまく適用できないかもしれません。
そのため、十分な資産を準備できる場合に限り検討できる戦略だといえます。
中長期的な売買戦略|成長投資枠を再利用する
成長投資枠で売買を繰り返しながら利益を狙い続ける方法も、NISAの出口戦略のひとつです。
成長投資枠は年間240万円という投資上限がありますが、保有している商品を売却すれば、売却した金額分を翌年以降に再利用できます。つまり、値上がりした商品を売却して得た利益で、新たな投資を続けられる仕組みなのです。
ただし、NISAで売買を繰り返す戦略には、以下のような注意点があります。
- 損失が生じる可能性がある
- 情報収集と市場分析が欠かせない
- 売却しても年間の投資上限額は240万円まで
- 損失が生じてもほかの所得との損益通算ができない
実践にはかなりの時間と労力がかかりますので、上級者向けの戦略です。
NISAで売買を繰り返す戦略は「新NISAはスイングトレードに不向き?活用のメリットと3つの戦略を紹介」の記事で詳しく解説しています。
一括で現金化する戦略|すべての商品を売る
これまでに積み立ててきた資産を、老後資金が必要になった時期にすべて売却して現金化する方法です。住宅の購入や教育資金など、まとまった資金が必要なタイミングでは、一度に現金化する方法が適しています。
しかし、老後の生活資金を確保するときは、一度にすべての資産を売却するのはおすすめできません。必要な金額だけ取り崩しながら運用を続けた方が、資産が増える可能性が高いからです。
また、物価上昇による資産の目減りを防ぐためにも、老後も資産運用を続けるのが効果的でしょう。
新NISAの取り崩しシミュレーション

老後の資金計画を立てるために、具体的な取り崩しのシミュレーションを見てみましょう。元本と取り崩し期間ごとに、毎月受け取れる金額を以下の表にまとめました。(※年利5%で仮定)
| 元本 | 20年間(毎月の受取額) | 30年間(毎月の受取額) |
| 1,000万円 | 約7万円 | 約5万円 |
| 1,500万円 | 約10万円 | 約8万円 |
| 2,000万円 | 約13万円 | 約11万円 |
元本と受け取り期間によって、毎月の受け取り金額は大きく異なります。ほかにも、年金や保険金の受け取りなど、NISA口座の取り崩しで必要となる老後資金は人それぞれ違います。
自分に必要な老後資金を把握し、NISAを辞めるタイミングでどのくらいの資産を作るべきか判断できるようにしておきましょう。
自分に必要な老後資金については「実際2,000万円で足りる?老後資金の算出方法や作り方徹底解説」で詳しく解説しています。
つみたてNISAと一般NISAの出口戦略

2023年まで運用を続けていた旧NISAでは、以下のような出口戦略がおすすめです。
- 一般NISAは早めに利益を確定させる
- つみたてNISAは20年間運用して売却する
旧NISAは非課税期間が決められているので、やめどきを理解しておけば、期間終了までに焦らず取り崩せるようになるでしょう。
一般NISAは早めに利益を確定させる
一般NISAの場合、含み益が出たタイミングでできるだけ早く売却するのがおすすめです。理由として、以下の3つが挙げられます。
- 値下がりのリスクが高いから
- 非課税での運用期間が5年と短いから
- ロールオーバーができなくなったから
とくに、一般NISAでは値動きの大きい商品に投資する方も多いです。5年後に非課税期間が終了するタイミングで株価が下がるリスクもあります。
「利益が10%出たら売る」や「1万円の利益が出たタイミングで売る」など、あらかじめ目標金額を決めておき、達成したタイミングで早めに売るのがおすすめです。新NISAの成長投資枠では、非課税で個別株やETFなどへの投資も可能なので、一般NISAの売却益で成長投資枠を活用するのも良いでしょう。
ただし、新NISAの年間投資上限である360万円を達成できる場合は、 そのまま特定口座で運用を続けるのも有効です。
つみたてNISAは20年間運用して売却する
つみたてNISAで運用している商品は、非課税期間ギリギリまで運用を続け、20年後に売却するのがおすすめです。投資信託を長期的に運用すれば、利益が生じる可能性が高いからです。
金融庁が行った過去の調査によると、投資信託を20年以上運用した場合、投資した金額を下回ることはないという結果が出ています。
長期的に資産を運用していれば利益が狙いやすいので、つみたてNISAは20年間の非課税期間を運用し、期間終了のタイミングで売却するのがおすすめです。
ただし、旧NISAと同様に、新NISAの年間投資上限額である360万円を達成できる場合は、 そのまま特定口座で運用を続けても良いでしょう。
新NISAの出口戦略で抑えておくべき2つのポイント

新NISAの出口戦略を考えるうえで、以下の2つのポイントを抑えておきましょう。
- 定期売却サービスを活用する
- 積立設定を解除する
それぞれ解説します。
定期売却サービスを活用する
NISAで運用した資産を老後の生活資金として取り崩すときは、定期売却サービスを活用するのがおすすめです。
定期売却サービスとは、積み立てた資産を毎月の受取額や売却タイミングを決めて自動的に現金化できるサービスです。証券会社の口座内で処理が完了するため、必要な金額を銀行に振り込むだけで老後の生活資金を確保できます。
設定できる売却パターンは、以下の3つです。
- 金額:毎月の受取額を指定する
- 期間:すべての資産を取り崩す期間を指定する
- 割合:すべての資産の中で取り崩す割合を指定する
楽天証券ではNISAで積み立てた資産の定期売却サービスを提供しており、SBI証券も来年には同じサービスを提供する予定です。
積立設定を解除する
NISA口座から資産を引き出しても、積立設定を解除しなければ毎月の積立は続きます。そのため、新規の積立をやめたいときは、証券会社のマイページで積立設定を解除しましょう。
証券会社ごとに操作方法は異なりますが、積み立て設定の一般的な解除方法は以下のとおりです。
- 証券会社のマイページにログイン
- 「取引の積立設定」から、積立を解除する銘柄を選択する
- 「積立設定の解除」を選択する
- 内容を確認し、取引パスワードを入力する
- 解除完了
資産を取り崩すときに積立設定を解除しておけば、効率的に現金を確保できます。
新NISAで資産を取り崩す3つのタイミング

新NISAで資産を取り崩すタイミングとして、以下の3つが挙げられます。
- ライフイベントで資金が必要なとき
- あと数年で老後を迎えるとき
- 70歳を過ぎたとき
取り崩すタイミングをいくつか知っておけば、自分に最適な出口戦略を考えられるようになるでしょう。
ライフイベントで資金が必要なとき
NISAは必要な資産を準備するための制度であり、目的が「老後資金の確保」以外であっても問題ありません。
マイホームの購入や結婚、子どもの教育資金など、ライフイベントで大きな支出が必要なタイミングであれば、NISAで運用した資産を取り崩すのも有効な使い方です。
もちろん、長期で運用した方が利益が膨らむ可能性はあります。それでも、資金が必要になればNISAで積み立てた資産を取り崩して使うのがおすすめです。
あと数年で老後を迎えるとき
残り数年で定年退職をして、老後を迎えるタイミングであれば、資産を少しずつ取り崩していくのが良いでしょう。いざ資金が必要なタイミングで株価が暴落していれば、現金で生活資金を確保できない可能性があるからです。
こちらの章で解説した「コア・サテライト戦略」と考え方は同じで、資金が必要な時期が近づくほど、現金や投資信託、債券などの低リスク資産の割合を徐々に増やしていくことが大切です。
老後の生活資金を確保できるよう、老後を迎える3〜5年前から徐々に取り崩しをするのも戦略のひとつと言えるでしょう。
70歳を過ぎたとき
定年後も働き続ける場合、70歳を目安に必要な金額だけを取り崩しながら運用を続けることをおすすめします。運用期間が長くなるほど、得られる利益が大きくなりやすいからです。
NISAで運用してきた資産は、あくまで必要な生活資金を補うためのものです。そのため、定年後も収入がある場合は、給料で賄えない分をNISAの資産から補うのが効率的な方法といえます。
NISAでも株の売る時が難しいものです。せっかく値上がりしたのに迷っている間に価格が下落してしまって売れないことが多いという方が多くいらっしゃいます。利益を確保するのは大事ですが、時には損切も必要になり、これができないと株で資産形成は難しくなります。しかし自分ではできないという方には、投資顧問の利用をおすすめします。当サイトを運営するライジングブル投資顧問は、株の「売買サポート」を行っております。ライジングブルの売買サポートサービスは、3ヶ月9,000円で買い推奨だけではなく、売却、銘柄入替するところまで、リスク管理をしながらサポートします。
個人の方には難しい売り推奨のアドバイス実績も豊富にあり、
・これから株をはじめる方
・株をやっているが資産が一向に増えない方
・損切ができず株を塩漬けにしがちの方
・損切ができない方
には、ライジングブルの売買サポートをおすすめします。
18年の歴史と3万人以上サポートしてきた実績で、少額資金ではじめても成功できるよう株の売買をサポートします
まとめ

NISAの非課税メリットを最大限引き出すためには、運用した資産をどう活用するかという出口戦略を考えることが欠かせません。せっかく積み立てた資産も、取り崩し方を間違えると期待したリターンを得られない可能性があります。
本記事では、5つの出口戦略を紹介しました。なかでも現実的な出口戦略は、個別株やETFの配当金を受け取る「インカムゲイン戦略」と、年齢とともに低リスク資産の比率を上げる「コア・サテライト戦略」です。
自分に合った戦略を用いることで、老後資金を確保しながら、結婚やマイホーム購入といったライフイベントにも対応できます。
新NISAは非課税期間が無期限になったことで、より柔軟な資産活用が可能な制度となりました。自分のライフプランに合わせた資産形成ができるように、少しずつ出口戦略を意識しながらNISAでの資産運用を続けていきましょう。


コメントComment