
「老後資金を貯めるためにやってはいけないことは何があるのだろう?」
老後資金を貯めたいけれど、不安を抱えてなかなか投資に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
結論、老後資金を貯めるためにやってはいけないことは7つあります。
老後の資産形成に関して、おすすめの正しい行動と改善策もあわせて解説しているので最後まで読んでみてください。
目次
老後資金を貯めるためにやってはいけないことは7つある

多くの方が陥りがちな、老後資金を貯めるためにやってはいけないことは以下7つです。
老後資金の準備は、一攫千金を狙うギャンブルではありません。長期的な視点で着実に資産を築いていくことが何よりも重要です。それぞれ解説します。
1.不自然に利回りの高い投資
老後資金を準備する際「年利20%は確実に得られる」「毎月5%の配当を元本保証する」といった、不自然に利回りの高い投資話に手をだしてはいけません。
実際には資金運用をおこなわず、新規の出資者から集めたお金を既存の出資者への配当に回す自転車操業的な手法「ポンジスキーム」の可能性があります。
ポンジ・スキーム(英: Ponzi scheme)は、投資詐欺の一種。新規投資家から集めた金を既存の投資家に支払う手法を指す。投資詐欺の9割がこの手法で行われる[1]。
ポンジ・スキームは新規出資者が集まらなくなった時点で成り立たなくなり、最終的には大きな金銭的被害がでます。
金融庁でも「元本が保証される」「高い配当を受けられる」などと謳う事業者と安易に契約しないよう、強く注意を喚起しています。
世界中のプロ投資家が、一般の個人投資家だけにリスクなく高収益がもたらされる話はしません。提示されたリターン価格が市場からかけ離れている場合、相応のリスクや詐欺の可能性を疑いましょう。
2.ハイリスク商品への投資
老後資金を貯めるために、次のようなハイリスク商品への集中投資は避けるべきです。
- FX(外国為替証拠金取引)
- 暗号資産(仮想通貨)
- 株式投資の信用取引 など
ハイリスク商品は短期間で大きな利益が期待できますが、大きく元本が減る、あるいは元本以上の損失が発生するリスクがあります。
老後資金は生活の基盤となる極めて重要な資金なので、投資に失敗した場合は生活が破綻しかねません。
とくに退職を控えた60代以降においては、被った損失を働いて補填していくのは困難になるでしょう。
そのため、老後資金はバランスの取れた株式投資や預金、債券などでバランスよく構築するのがおすすめです。ハイリスク商品は、資産全体のごく一部の余裕資金で取り組む程度に留めておきましょう。
3.節税効果を目的とした投資
節税効果を目的とした投資は非常に魅力的に聞こえますが危険を伴うため、老後資金の形成には向きません。一部の保険商品や不動産投資では、高い節税効果がアピールされていますが、高い手数料がかかっていたり、投資対象の収益が低かったりするケースも少なくありません。
投資の本来の目的は「資産を増やすこと」であり、節税効果はあくまで付加的なメリットです。節税効果を優先するあまり収益性の低い商品やリスクの高い商品を選択しては、資産形成という本来の目的を見失います。
老後資金の準備においては節税を目的とした投資ではなく、資産形成をしっかりできる投資商品を選ぶようにしてください。
4.現金化に時間がかかる投資
現金化に時間がかかる投資は急に現金が必要になった際、頼りにならないため注意が必要です。老後は、現役時代には想定しなかった急な出費が、以下のように発生する可能性があります。
| 医療費 | 入院一回あたり:平均19.8万円 | ・入院時の自己負担費用 ・高額療養費制度の対象外となる差額ベッド代 ・先進医療費は全額自己負担となり100万円を超えるケースもある |
| 介護費用 | 一時費用:平均74万円月額費用:平均8.3万円< | ・在宅介護のための住宅改修や介護用品の購入 ・介護施設への入居一時金 ・介護状態が続けば月々の費用も継続的に発生する |
| 住宅リフォーム | 一回:50万~300万円 | ・加齢に伴う身体機能の低下に対応するためのバリアフリー化(手すり設置、段差解消など) ・水回り設備の交換費用 |
| その他 | 状況に応じて100万円以上 | ・子や孫への資金援助 ・自身の葬儀費用の準備 ・ライフイベントに応じた支出 |
参考元:令和4年度「生活保障に関する調査」(速報版)|生命保険文化センター
参考元:2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」|生命保険文化センター
上記のような場合、想定以上の費用が必要になる可能性もあります。そのため、不動産投資や仮想通貨などの仕組みが複雑な金融商品ばかり保持している場合は、すぐに現金化できずに本当に資金が必要な際に困ります。
こうした事態に備えるためにも、必要なときにすぐ現金化できる預金や株式資産などを一定額確保しておくのが重要です。
5.退職金の一括投資
長年勤め上げた証である退職金の多くが数千万円単位のまとまった金額になりますが、金融商品に一括投資するのは非常に危険な行為です。
退職金を受け取ると、金融機関から金融商品加入の熱心な営業を受ける機会が増えます。もし、退職金を利用し投資したタイミングが悪く直後に市場が暴落した場合、資産が大きく減るため精神的なダメージも計り知れません。
実際、金融庁も退職金の運用について以下のように注意を促しています。
高齢期に有する資産の多くは、それまでの就労の対価として得たものであり、高齢期における生活の糧として極めて重要なものである。
特に、退職金の受取りは、多くの方にとって、まとまった資金での投資を始める一つのきっかけとなるが、十分な知識がないまま、仕組みの複雑な商品やリスクの高い商品に投資し、損失を被る例も見られる。
退職金のような大きな金額を再度取り戻そうとしても、定年しているため同じ額を稼ぐにはビジネスで成功するかなど不確定要素が強いものしかありません。
退職金は安全な預貯金と投資に使い分けたうえ、冷静に時間をかけて自分に合った資産運用を検討しましょう。
6.手数料負けしてしまう金融商品での投資
手数料負けしてしまう金融商品での投資は、運用がうまくいっても手元に残る利益がほとんどなくなる恐れがあるため避けるのが無難でしょう。
とくに注意が必要なのは、以下のような商品です。
- 販売手数料が高い商品
- 信託報酬(運用管理費用)が高い商品
- 変額保険や外貨建て保険の一部
長期運用になればなるほど、このわずかな手数料の差が最終的な資産額に大きな影響を与えます。このため、どの金融商品に投資するのかはしっかり見定めたうえで決めましょう。
7.たこ足ファンドでの投資
「たこ足ファンド」への投資も、気づかぬうちに資産が減る可能性があるため避けるべきです。
たこ足ファンドとは資産運用によって得られた利益ではなく、投資家から預かったお金(元本)を取り崩して、あたかも利益がでたかのように分配金を支払う投資を指します。
指定の独立行政法人国民生活センターの広報誌『国民生活』2025年1月号でも、資産形成に関する特集の中で注意喚起が促されていました。
しかし、分配金には投資信託の運用で得られた利益から支払われる「普通分配金」と元本の一部を取り崩して支払われる「特別分配金」の2種類があります。
特別分配金は自身が投資したお金が戻ってきているだけであり、利益ではありません。仕組みを理解せずに投資を続けると、資産が増えていると誤解したまま元本を減らしてしまう危険性もあるでしょう。
分配金を受け取るときは、内訳が普通分配金か特別分配金かを確認し、資産全体が着実に増加しているか見極めてください。
老後の資産形成に関しておすすめの正しい行動と改善策

次に老後の資産形成のために取るべき正しい行動と、改善策をそれぞれ紹介します。
- 収支を見直して「毎月の貯蓄額」を確保する
- 少額から投資をはじめて「お金にも働いてもらう」
- 老後にかかるお金の「目安金額」を把握する
- 長く働ける環境を整えておく(収入を維持する)
- 信頼できる専門家の助言を受ける
着実かつ安全に老後資金をつくるために、要点を押さえましょう。
1.収支を見直して「毎月の貯蓄額」を確保する
老後の資産形成をスムーズに実施するには、家計の収支を見直して「いくらなら毎月貯蓄や投資に回せるか」を明確にし「毎月の貯蓄額」を確保しましょう。
資産形成のすべての土台となるのは、安定した貯蓄です。総務省の家計調査(2023年)によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の消費支出は月平均で約25万円です。
家庭の支出を家計簿アプリで「見える化」し平均的なデータと比較しながら、無駄な固定費(通信費、保険料など)や変動費(食費、交際費など)がないかを見直しましょう。
収入から貯蓄額を先に引き、残ったお金で生活する「先取り貯蓄」の習慣化が、着実に貯蓄額を確保するコツです。
参考元:家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要|金融庁総務省統計局
2.少額から投資をはじめて「お金にも働いてもらう」
低金利時代の現在、預貯金に加えて少額からでも投資をはじめ「お金にも働いてもらう」視点が重要です。貯蓄だけで老後資金を準備するのは、インフレ(物価上昇)によりお金の価値が下がるリスクを考えると非効率です。
政府は個人の資産形成を後押しするために設けた「NISA(少額投資非課税制度)」の活用が有効とされています。
金融庁の資料にも示されているとおり、2024年から開始された新NISAには以下のような特徴があります。
新NISAのポイント
- 制度の恒久化・非課税保有期間の無期限化
- 年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:120万円、成長投資枠:240万円)
- 非課税保有限度額は全体で1,800万円
非課税で投資できる金額が大幅に拡大し、いつでもはじめられる恒久的な制度になったので、新NISAは長期的に資産形成していくうえで有効な手段になるでしょう。
まずは月々5,000円や1万円といった無理のない金額から、投資にチャレンジしてみてください。
3.老後にかかるお金の「目安金額」を把握する
漠然とした老後資金への不安解消のためにも、老後にかかるお金の「目安金額」を把握しましょう。老後の生活費は、どの程度の暮らしを望むかによって大きく変わります。
生命保険文化センターによると、夫婦二人の老後生活費は以下のとおりです。
- 最低日常生活費:月額で平均23.2万円
- ゆとりある老後生活費:月額で平均37.9万円
上記の結果から「ゆとりある老後生活」を送りたい場合、公的年金の受給額だけで生活する際は不足分を自身で準備する必要があります。
自身の正確な年金見込額は、日本年金機構が運営する「ねんきんネット」で確認できるため、理想の生活レベルと照らし合わせたうえ、具体的な目標金額を設定しましょう。
4.長く働ける環境を整えておく(収入を維持する)
働ける年数を増やして収入を確保し資産に手をつけるのを遅らせれば、資産を長持ちさせられます。
実際、高年齢者雇用安定法が改正され、高年齢者の就業環境は整備されつつあります。厚生労働省は事業主が講ずるべき措置(努力義務)として、以下の選択肢を提示しているようです。
70歳までの就業機会の確保(努力義務)
70歳までの定年引上げ定年制の廃止
70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊な雇用形態として)
70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
現代は希望すれば長く働き続けやすい社会環境が整いつつあり、定年後の再雇用や再就職に加え、これまでのスキルを活かしたフリーランスへの転身や起業など、選択肢は広がっています。
希望の働き方を実現するためにも健康管理に気を付け、長期間働けるように心がけてみてください。
5. 信頼できる専門家の助言を受ける
代表的な専門家として、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)やFP(ファイナンシャルプランナー)が挙げられます。
| IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー) | ・内閣総理大臣の登録を受けた金融の専門家・特定の金融機関の方針に縛られずない・独立や中立な立場から顧客一人ひとりのライフプランに合わせた資産運用のアドバイスを実施する |
| FP(ファイナンシャルプランナー) | ・一人ひとりに関する将来の夢や目標に対してお金の面でさまざまな悩みをサポートし、解決策をアドバイスする・家計管理から教育資金、住宅ローン、老後資金までお金に関する幅広い相談に応じる |
もし、うまく老後資金を投資したい場合は相談する前に、依頼する専門家がどのような資格を持っているのか(CFP®、AFP、FP技能士1級など)や得意分野、相談料を確認しましょう。
関連記事
資産運用の相談はどこが安心?おすすめ相談先ランキング|5選
ここまで、老後の資産形成のためにおすすめの正しい行動と改善策を紹介してきました。次章では、怪しい老後資金に関する投資詐欺の特徴について解説します。
怪しい老後資金に関する投資詐欺の特徴

大切な老後資金に関する怪しい投資詐欺は、以下3つの特徴があります。
老後資金を狙う投資詐欺は年々手口が巧妙化しているので、十分に注意しましょう。
「絶対に儲かる」「元本保証」などリスクゼロを強調してくる
「絶対に儲かる」「元本保証」などリスクがない内容を強調する投資勧誘は、法律で明確に禁止されている違法行為であり詐欺の典型的な手口です。
金融商品取引法では事業者が将来どうなるか不確実なことについて「絶対にこうなります」と決めつけて、投資勧誘を行うのを「断定的判断の提供等の禁止」(法第38条第2号)で厳しく禁じています。
(断定的判断の提供等の禁止)
「必ず儲かる」「絶対損はしない」といったセールストークのように、顧客に対し、有価証券等の値動きやその分析等について、断定的な表現を用いて勧誘を行うことは、投資者の投資判断を誤らせ、投資者保護上、重大な問題がある。
このようにすべての投資には必ず利益が出る金融商品はなく、価格変動のリスクが伴います。
リスクが存在しないかのような説明で勧誘してくる場合、事業者は法律を守る意識がない、あるいは投資家の損失を意図した詐欺である可能性が極めて高いでしょう。
そのほかにも近年では、SNS上で著名人になりすまし「元本保証で月利10%」といった非現実的な条件で勧誘する手口も急増しています。
どのような状況であれ、リスクがないことを強調された場合は直ちに詐欺を疑い、決して契約しないようにしてください。
金融庁に登録されていない
金融庁に登録されていない事業者は、法律を無視して営業する違法な「ヤミ金融(無登録業者)」であり関わりをもってはいけません。
日本国内で投資運用業や投資助言業などの金融商品取引業を実施するには、金融商品取引法に基づき金融庁(財務局)への登録が義務付けられています。
無登録業者は法律を守る意思がなく、詐欺や悪質なトラブルに発展する可能性が極めて高いです。実際、金融庁も無登録業者について以下のように強く警告しています。
無登録の業者との取引で、「出資金をだまし取られた」「解約したくても応じてもらえない」「業者と連絡が取れなくなった」といったトラブルが多発しています。
無登録業者からの勧誘は、絶対に相手にしないでください。
ヤミ金融(無登録業者)は投資資金の持ち逃げ、法外な手数料の請求、個人情報の悪用といった手口で、深刻な被害をもたらします。
少しでも怪しいと感じたら契約する前に、必ず金融庁のウェブサイト「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で業者名や電話番号を検索し、正規の登録業者であるか確認しましょう。
利益が出たと言っているのに出金ができない
利益が出たと言っているのに「税金がかかる」「手数料が必要」など、さまざまな理由をつけて出金を拒否する手口は典型的な投資詐欺です。
最初に少額の利益を出金させて信用させ、より高額な投資をさせた後、まとまった金額を出金しようとすると拒否するパターンが多くあります。
とくに「利益を引き出すために追加の入金が必要」という要求は、詐欺と断定できる重要なサインです。この手口について、独立行政法人国民生活センターも以下のように強く警告しています。
利益分を出金しようとすると「利益に対して税金がかかる」「出金手数料が必要」など、さまざまな名目をつけて送金を要求されるケースがみられます。
送金しても、さらに「システム手数料」「保証金」などと次々に理由をつけて送金を要求され、最終的に事業者と連絡が取れなくなるケースがほとんどです。
犯人の目的は税金や手数料の支払いではなく、被害者からさらにお金をだまし取ることです。一度支払っても、別の名目で次々と支払いを要求され、被害が拡大するだけです。
いかなる名目であれ、出金のために追加の支払いを求められた時点で詐欺と判断し、絶対に応じないでください。すぐに取引を中止し、最寄りの警察署や国民生活センター、金融サービス利用者相談室などに相談しましょう。
老後資金を貯めるためにやってはいけないことに関するよくある質問

老後資金を貯めるためにやってはいけないことに関する、よくある質問に回答します。
60歳で8,000万円の金融資産があったら足りますか?
60歳で8,000万円を運用しながら取り崩した場合に毎月使える金額は、運用利回りによって大きく変わります。
金融庁のNISA特設ウェブサイト上で提供されている「ライフプランシミュレーター」を用いて算出できます。たとえば、年率3%で運用しながら30年間で取り崩す場合、毎月約35.5万円を使える計算です。
「ライフプランシミュレーター」は、「とりくずしシミュレーション」機能を備えており、初期投資額、想定利回り取り崩し期間を入力すると、毎月の受取額や資産の推移を手軽に計算できる公式ツールです。
実際に「ライフプランシミュレーター」で以下の条件を入力して試算します。
- 初期資産額:8,000万円
- 想定利回り:3%
- 取り崩し年数:30年
上記の条件で試算すると「毎月の取り崩し額:355,593円」と算出され、30年間の受取総額は約1億2,800万円となります。
運用によって約4,800万円の利益が上乗せされた結果です。(※税金や手数料は考慮していません)
もし運用せず(年率0%)に取り崩す場合は、単純計算で月々約22.2万円(8,000万円 ÷ 30年 ÷ 12ヵ月)です。運用するかしないかで、毎月の生活費に13万円以上の差が生まれる可能性もあるでしょう。そのためどれくらいの運用利回りで運用できるのか?毎月いくら生活費が必要なのかにより判断が分かれるところです。
70歳で4,000万円以上貯金している割合は?
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、70歳で金融資産を4,000万円以上貯金している世帯の割合は以下のとおりです。
- 二人以上世帯:17.5%
- 単身世帯:11.2%
そのため、70代だからといって4,000万円以上の資産を持つ世帯は多くはありません。周囲と比較して焦る必要はありませんが、老後資金の準備は計画的におこなっていきましょう。
参考元:家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)|[単身世帯調査](令和5年)金融広報中央委員会
高齢者がやってはいけない投資は?
本記事で解説した内容と同様に、とくに高齢者がやってはいけない投資は以下の3点です。
| ハイリスク・短期勝負の投資 | ・FX、暗号資産、個別株の信用取引など |
| 高手数料・複雑な商品 | ・ラップ口座、仕組みがわかりにくい保険商品など ・コストがリターンを圧迫し、実質的な利益が少なくなりがち |
| 流動性の低い投資 | ・非上場の不動産や株式など ・急な医療費や介護費が必要になった際に、すぐ現金化できないリスクがある |
老後資金は基本、比較的リスクの低い投資運用で堅実に形成し、大部分はいつでも引き出せる預貯金で確保しておくのがバランスのとれた資産配分です。
まとめ:老後資金を効率よく貯めるには見極めが重要

結論、老後資金を貯めるためにやってはいけないことは7つあります。
老後資金を効率よく貯めるにも、やるべき内容とやるべきでない内容をきちんと精査したうえ老後資金を貯めるようにしましょう。
弊社では月あたり3,000円の会費(3か月9,000円)で、投資顧問サービスを提供しており、多くのお客様からご満足いただいております。老後資産の運用に株式投資をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
また、LINEで資産運用に関する情報も無料で提供しているので、気になる方は登録して資産運用に関する情報を勉強してみてはいかがでしょうか

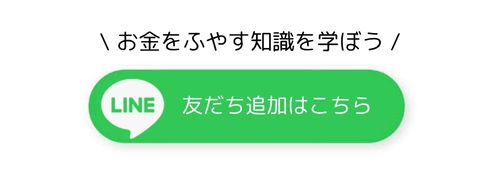

コメントComment