
株価の回復が見込めない場合、これ以上の損失を出さないために「損切り」をするのも選択肢のひとつです。
しかし、損切りは損失を確定させる行為なので、なかには「もう少し待てば戻るかも」「売った直後に値上がりしたら嫌だ」と考えてズルズルと持ち続けている人もいるでしょう。
損切りをすべきかどうかは投資の目的や資産状況によって異なるため、明確な答えがないのも事実です。
そこで本記事では、損切りした方が良いケースとすべきでないケースについて解説します。
損切りのメリット・デメリットについても解説しているので、自分にとって最適な「損切りライン」を決めるための参考にしてみてください。
損切りはしない方が良いのか【結論】
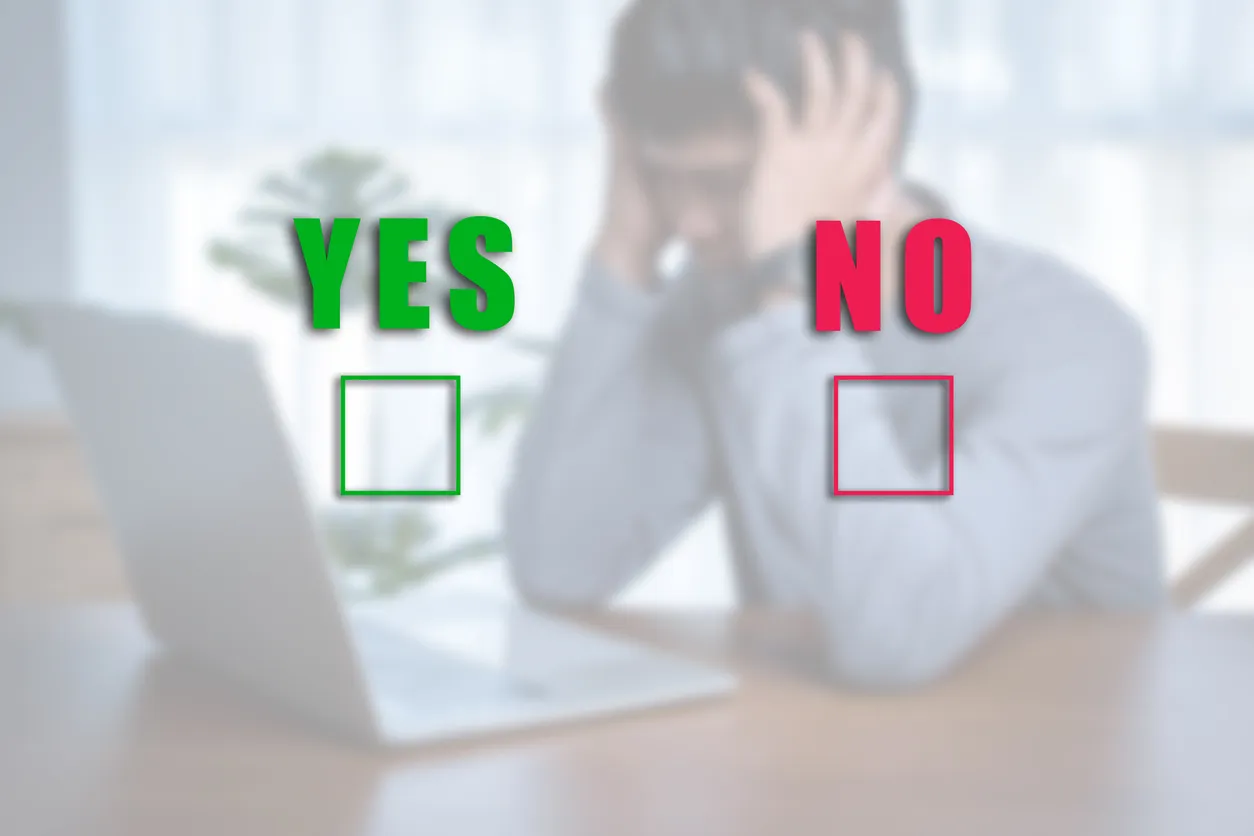
「株で損切りはしない方が良いのか?」に対する回答は、個人の目的や資産状況によって異なると言えるでしょう。
損失が拡大しそうなら損切りするべきですし、回復が見込めるのなら保有し続けるべきです。
本章では「損切りしない方が良いケース」と「損切りした方が良いケース」の具体例をそれぞれ紹介します。
損切りしない方が良いケース
株式投資で損切りしない方が良い・すべきでないケースとしては、以下が挙げられます。
- 少額投資で含み損が少ない
- 投資資金にまだ余裕がある
- 長期目線で利益を狙っている
- 配当利回りや株主優待で収入が期待できる
- NISA口座で運用している(つみたて投資枠)
- 企業の売上や利益が安定していて将来性に問題がない
とくに、NISA口座で投資する場合、基本的には損切りしない方が良いでしょう。
NISA制度自体が「長期運用」を前提としており、つみたて投資枠の対象商品については「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」※に限られます。また、NISAでは損益通算(ほかの利益との相殺)ができないので、ほかの取引口座(一般口座/特定口座)に比べて損切りのメリットが少ないです。
NISA口座では一時的な含み損が生じたときでも、無理のない範囲で運用し続けた方が長期的に利益を狙えるでしょう。
損切りした方が良いケース
株式投資で損切りした方が良いケースは、以下のとおりです。
- 企業の業績が継続的に悪化している
- リスク許容度を超えた含み損が生じている
- もっと利益が見込めそうな投資先に切り替えたい
- トレンドの変化で業界への注目度が下がっている
なかでも「リスク許容度を超える含み損が出たとき」は、早めの損切りをおすすめします。
不安になるほどの損失が出ていると常に株価が気になり、仕事や私生活に集中できなくなる可能性があるからです。
睡眠不足や集中力の低下などの悪影響が出ないように、含み損に対して強いストレスを感じるときは、早めの損切りで気持ちを切り替えましょう。
一度、冷静になってから投資戦略を見直せば、利益が見込めるほかの投資先に挑戦できるようになるはずです。
損切りしないと生じる5つのデメリット・リスク

株を損切りせずに持ち続けていると、以下の5つのデメリットが生じます。
上記を理解したうえで「損切りすべきかどうか」を判断すれば、株式投資で失敗するリスクを減らせるでしょう。
損失額が増え続ける
損切りしない戦略には、損失額がどんどん増え続けるリスクがあります。
実際に、トレンドの変化や経営陣の交代などに対応できず、株価が暴落して回復できなくなった投資先はいくつもあります。
将来性の低い株は株価の回復が見込めないため、売らずに持ち続けても利益を狙いにくいでしょう。
新たな投資先に挑戦できなくなる
損切りしない場合、新たな投資に挑戦しにくくなります。現金を確保できず、利益が見込めそうな他銘柄を買うための資金に余裕がなくなるからです。
確かに「まだ回復するかもしれない」と思うと、なかなか損切りに踏み切れないものです。
しかし、含み損で投資資金を動かせずにいると、追加の資金確保のための家計を圧迫したり借金したりするリスクが生じます。
結果、無理な投資によって損失を広げる可能性があります。
不安やストレスで冷静な判断ができなくなる
含み損によって不安やストレスが続くと、冷静な投資判断ができなくなる可能性があります。
たとえば、損失を打ち消すために買い増したり、値動きの大きい他銘柄を買ったりと、ハイリスクな投資行動に走りがちです。
感情的な投資をすると損失が広がる可能性もあるので、不安な気持ちが強いときは早めの損切りを検討すべきでしょう。
いつまでも含み損が続く状態になる|塩漬け
損切りをしないと、株を「塩漬け」にする可能性があります。株の塩漬けとは、損失を確定させるのが怖くて、売却できずに持ち続けている状態のことです。
いつまでも含み損を抱えることになり、気持ちも投資戦略も切り替えられません。
結果、何年も利益が出ない状態で放置することになり、投資の意味がなくなってしまいます。
塩漬け状態の株にお悩みの方はこちらの記事も参考に【塩漬け株に悩む方】株の損切りができない本当の理由と損切りラインの見極めポイントを実例をまじえて解説
損を取り返すための買い増しで損失が膨らむ|ナンピン買い
含み損を放置すると、ナンピン買いによって損失を膨らませるリスクがあります。
ナンピン買いとは、値下がりしている株をあえて買い足して「平均購入株価」を下げる手法です。
含み損を取り返せるかもしれませんが、株価がさらに下落するとかえって損失額を増やしてしまいます。
含み損によって感情的に売買してしまうことは、損切りしないことで生じるリスクのひとつと言えるでしょう。
損切りしないで待つことの4つのメリット

損切りをせずに待つスタイルには、以下の4つのメリットがあります。
損切りの必要性を判断するための参考にしてみてください。
長期で見るとリターンが期待できる
銘柄によっては、損切りせずに長期保有することで利益を狙える場合があります。
一例として、全世界株式インデックスファンド「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」の価格チャートをご覧ください。
短期的な下落はあるものの、長期的には右肩上がりで成長しています。
とくに、インデックスファンドには長期運用を見据えた商品が多いため、頻繁に損切りをすると利益を逃すことになるかもしれません。
成長性のある銘柄を見つけられれば、損切りしない方が利益を狙える可能性があります。
日々の値動きに一喜一憂しなくなる
長期運用の投資スタイルでは、日々の値動きに一喜一憂しなくなります。
あくまで数年後の成長を見込んで投資しているため、日々の値動きは長期的に見ると一時的なものだからです。
株の値動きを気にしなくなると「損するのが怖い」といった精神的ストレスが減り、冷静な投資判断ができるようになるでしょう。
配当金や株主優待を継続して受け取れる
損切りせず株を持ち続けていると、配当金や株主優待を継続して受け取れる可能性があります。
株を手放さない限り、企業が利益を出している間は配当金や株主優待の対象となるからです。
年1〜2回ほど現金を受け取れたり、企業の商品券や割引クーポンなどの特典を受けられたりするため、株価が下がっているときでもメリットを受けられます。
配当金や株主優待が充実している銘柄なら、株の値下がりによる損失を相殺できるかもしれません。
運用コストを節約できる|売買手数料や売買判断
損切りせず待ち続けると、運用コストを節約できる可能性があります。売買ごとに、手数料や判断が必要になる場合があるからです。以下の表では、株や投資信託の売買で発生するおもな手数料をまとめました。
| 取引内容 | 手数料 |
| 国内株式の売買 | ・売買手数料 |
| 海外株式の売買 | ・売買手数料 ・為替手数料 |
| 投資信託の売買 | ・信託財産留保額(売却/解約時) |
取引ごとに一定額の手数料が発生すると、損切りして他銘柄に買い換えるときに手数料がかさむ可能性があります。
また、損切りには売るタイミングの判断や新たな銘柄選び、実際の取引操作といった作業コストも発生します。
損切りしない長期運用スタイルなら、手数料でも作業時間でもコストを削減できるはずです。
自分にあった損切りルールの決め方3選

損切りルールは、単純に「5%下落したら損切り」のように一律で決めるものではありません。重要なのは、運用資産全体における投資比重を考慮することです。ここでは、資産状況に応じた実践的な損切りルールの決め方やトレンドの変化に応じた損切ルールの決め方を3つ紹介します。
大きな損失を出さないために、上記の選択肢を知ったうえで投資に挑戦しましょう。
投資比重に応じて損切りラインを調整する
損切りラインは、その銘柄が運用資産全体に占める割合によって変えるべきです。
具体例(運用資産1,000万円の場合)
①A銘柄を株価1,000円で500株購入(投資額50万円=資産の5%) その後、株価が800円に下落した場合
- 損失:10万円((1,000円-800円)×500株)
- 資産全体に占める損失の割合:1%
②A銘柄を株価1,000円で10,000株購入(投資額1,000万円=資産の100%) その後、株価が800円に下落した場合
- 損失:200万円((1,000円-800円)×10,000株)
- 資産全体に占める損失の割合:20%
①のケースでは、運用資産の1%の損失なので取り戻すことはそれほど難しくありません。様子を見るという選択肢も取れます。一方、②のケースでは損失が資産の20%と大きく膨らんでおり、取り戻すことが非常に困難です。このケースでは、ここまで損失が拡大する前に損切りしておく必要があったと言えます。
推奨される損切りライン
投資比重に応じた損切りラインの一例は以下の通りです:
- 資産の100%を投資している場合:3〜5%の下落で損切り
- 資産の50%を投資している場合:5〜8%の下落で損切り
- 資産の10%を投資している場合:10〜15%の下落で損切り
資産全体の中で全額の100%を投資しているのであれば3~5%のラインで損切り、50%であれば5~8%のラインで損切り、10%であれば10%~15%で損切りというように、自分なりのラインを決めておくことがよいでしょう。
自分のリスク許容度から逆算する
損切りルールを決める際は、「どこまでの損失なら精神的に耐えられるか」を基準に考えることも重要です。こちらは運用資産全体で許容できる損失額を決め、その範囲内で、各銘柄への投資額と損切りラインを設定する方法です。複数銘柄に分散投資する場合、各銘柄の損失額の合計が許容範囲を超えないように調整しましょう。
(具体例)
50万円の損失までしか耐えられないと決めた場合:
- A銘柄(投資額300万円)の損切りライン:10%の下落(損失30万円)
- B銘柄(投資額200万円)の損切りライン:10%の下落(損失20万円)
- 合計の最大損失:50万円
このように、精神的な負担を軽減しながら投資を続けられるラインを設定しましょう。
業績や市場トレンドの変化で判断する|ファンダメンタルズ分析
根拠のある損切りラインを決めるためには、ファンダメンタルズ分析が欠かせません。
ファンダメンタルズ分析とは、企業の業績や財務状況、市場の変化などをチェックし、値動きを予測する分析方法です。
感情的な判断ではなく、データに基づいて損切りラインを決めるので、損失が大きくなる前に根拠を持って見切りをつけられます。
とくに、ファンダメンタルズで以下のような結果が出た場合、損切りを検討しましょう。
- 営業利益や純利益が複数期連続で減少している
- 会社の不祥事や経営陣の問題行動が続いている
- トレンドによって主力事業の市場が縮小している
分析したうえで「株価の回復は難しい」と考えられるときは、早めの損切りが有効です。
ファンダメンタルズ分析の詳細は、こちらの「株初心者向け、ファンダメンタルズ分析とは?どうやって株価の予測に役立てるのかをわかりやすく解説」記事で解説しています。
損切りに関するよくある質問
損切りに関するよくある質問に回答します。
それぞれ見ていきましょう。
金持ちは損切りしないって本当?
結論、金持ちの投資家にも損切りする方は多いです。
とくに、個別株投資においては株価の予想が難しいため、プロの投資家でも予想を外すケースがあります。
損失を広げないため、新たな投資先に資金を回すためにも、損切りは金持ちにも必要な選択肢だと言えるでしょう。
株の20パーセントルールで損切りしても良い?
弊社では運用資産全体における投資比重を考慮して損切ルールをおすすめしておりますので、この方法はおすすめできません。
そう言われても、株式投資では損切ができずに塩漬け株にしてしまうことが多いという方には、信頼がおける投資アドバイザーへの相談がおすすめです。最近、怪しいアドバイス先が多くどこに相談したらいいかわからないという方も多いと思います。信頼できる投資顧問会社は?を探したい方はこちら。当社の口コミを確認したい方はお客様の声をご確認ください。 当サイトを運営するライジングブル投資顧問は、株の「売買サポート」を行っております。ライジングブルの売買サポートサービスは、3ヶ月9,000円で買い推奨だけではなく、売却、銘柄入替するところまで、リスク管理をしながらサポートします。
個人の方には難しい売り推奨のアドバイス実績も豊富にあり、
・これから株をはじめる方
・株をやっているが資産が一向に増えない方
・損切ができず株を塩漬けにしがちの方
・損切ができない方
には、ライジングブルの売買サポートをおすすめします。
18年の歴史と3万人以上サポートしてきた実績で、少額資金ではじめても成功できるよう株の売買をサポートします
まとめ

損切りするかしないかについての回答は、個人の状況によって異なります。
個別株には値動きが大きいものもあるため、短期投資では損切りラインを決めるべきです。
一方で、長期運用なら一時的な値動きに左右されず、淡々と積立投資を続けた方がリターンを狙えます。
しかし、長期投資でも自分なりの損切りルールを決めておくべきです。
損失が想定を大きく超えたり、投資先の将来性がなくなったりした場合には、長期投資であっても損切りが必要になるからです。
生活資金に余裕のある状態で老後を迎えられるよう、損切りや投資の基本を理解し、自分に合った運用スタイルを見つけましょう。

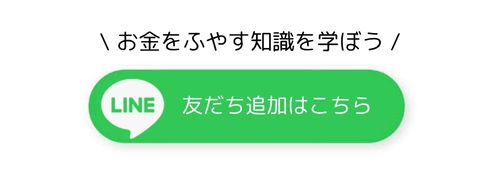

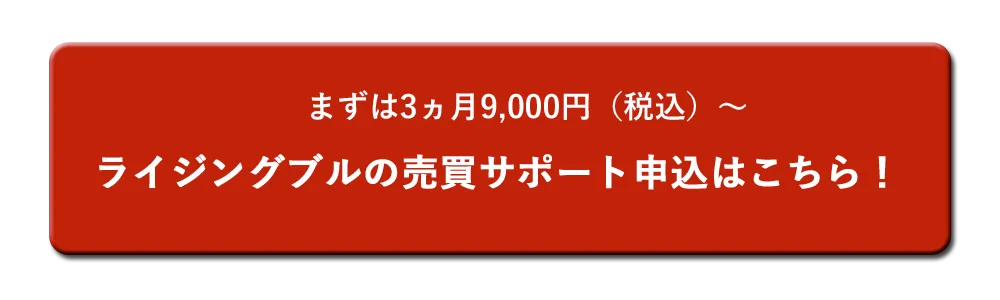

コメントComment