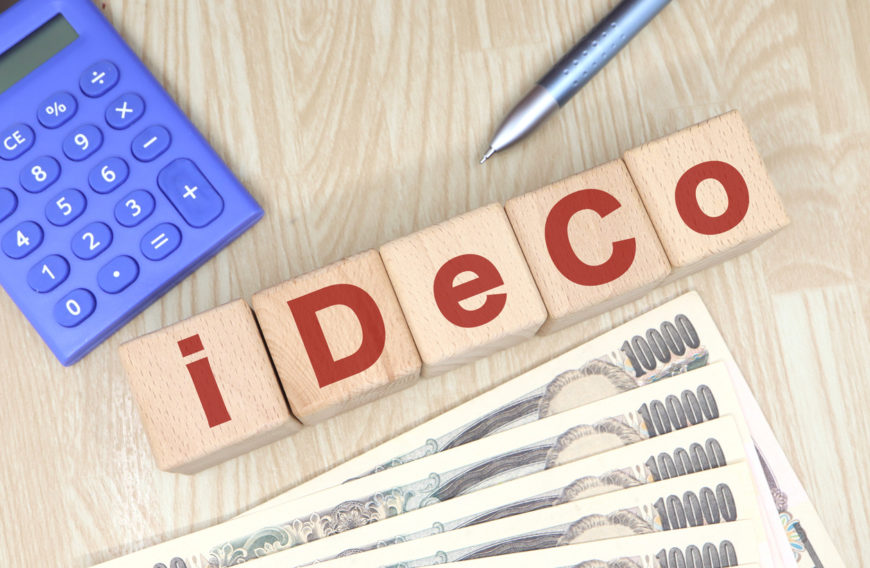
iDeCoは掛け金が所得控除の対象になったり、運用益が非課税になったりとメリットの多い制度です。
ただし、専業主婦(主夫)の場合、収入が少なく所得控除の恩恵が受けられません。「老後のお金が不安…」「投資を始めたいけど、扶養から外れたくない…」などの悩みがあっても活用するべきか迷いますよね。
そこで今回は、専業主婦(主夫)の方向けに、iDeCoに加入するメリットや活用方法を解説します。加入にはデメリットもありますので、内容をよく確認してから対応しましょう。
iDeCoの基本的な制度について知りたい方は「老後資金を作るならiDeCo(イデコ)の活用を!拠出限度額など最新情報を紹介」をご確認ください。
目次
専業主婦でもiDeCoを始められる?

「専業主婦だと、iDeCoに加入できないのでは…」「パートで働いていても、扶養から外れたくないから無理かも…」そんな不安を持っている方も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、専業主婦の方でもiDeCoを始められます。ただし、いくつかの条件を確認する必要があります。
専業主婦のiDeCo加入資格
もともとiDeCoは専業主婦の加入が認められていませんでした。しかし2017年1月の制度改正で認められ、専業主婦でも老後の資産形成ができます。
無収入やパート収入の場合、所得控除が受けられないデメリットはあるものの、運用益が課税対象にならないなどメリットも多い制度です。
パートで働いている場合の収入制限
パートの場合は、所得控除が受けられる年間103万円以内で働くことが多いと思いますが、iDeCoに加入していれば、103万円を超えた分についても所得控除が受けられるようになります。
ただし、106万円を超えた場合、働いている事業所の規模が従業員数51人以上(2024年10月以降)、月額の賃金が88,000円以上の場合は、社会保険料が発生します。
また、年間の収入が130万円を超えた場合は、事業所の規模に関わらずの第3号被保険者に該当しなくなり、社会保険料が発生しますので、注意が必要です。
主婦がiDeCoを始めるメリット

「iDeCoは始められるとわかったけど、本当に始める価値はあるの?」というのが次の疑問ではないでしょうか。主婦がiDeCoを始めることには、税金面での優遇や将来設計において多くのメリットがあります。いくつかのメリットを紹介します。
節税対策ができる
iDeCoで資産運用する一番のメリットは節税対策です。専業主婦やパートで働いている場合は、収入がそれほど高くないため、所得控除の恩恵は受けられませんが、運用益に対する税金は免除されます。
株などの投資における利益については、通常所得税と住民税を合わせて、20.315%の税金がかかります。株式の運用で100万円の利益が出た場合は、203,150円もの税金を納めなければなりません。
これに対してiDeCoで運用した場合は、この税金が免除されます。かなりの大きな差がありますよね。
そのほか、パートでも103万円を超える労働をした場合は、超えた分に対して所得税がかかりますが、iDeCoの掛け金と組み合わせると所得税を減らせます。
毎月2万円をiDeCoで積み立てた場合、年間の掛け金は24万円となります。所得税がかからない年間の収入は103万円ですが、これにiDeCoで積み立てた24万をプラスして、103万円+24万円=127万円まで非課税の対象に拡大できます。
ただし、106万円を超える収入には、事業所の規模によって社会保険の支払いが発生しますので、どちらが得になるか長期的に計算をして対応する必要があることには注意しましょう。
資産形成になる
2つめのiDeCoメリットとしては、iDeCoの本来の目的である資産形成になることがあげられます。iDeCoは個人年金を拡大するためにできた制度であり、老後の年金不足を補うために資産形成をする制度です。
さらに毎月一定額を積み立て、複利で運用することで資産を大きく伸ばせます。
例えば、40歳の主婦が60歳まで20年間毎月2万円をiDeCoで積み立て、3%の複利で運用した場合は、積立金の合計は480万ですが、運用益を合わせると657万円まで増やせます。
さらにこの運用益は課税されませんので、そのまま657万円が受け取れます。これは老後の生活資金としては心強い味方になるでしょう。
受け取り時の税制優遇となる
退職金制度のない専業主婦でも、iDeCoで資産を作れば受け取り時に「退職金所得控除」が適用されます。
退職金所得控除とは、会社を定年退職する際に、勤続年数に応じて所得控除が適用される制度です。退職金所得控除は勤続年数に応じて計算されますが、専業主婦の場合はiDeCoの加入期間を勤続年数として計算します。
| 勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×A(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(Aー20年) |
先ほどの例でいえば、20年間の積み立てとなるため、40万円×20=800万円が控除対象です。運用益を含めた合計金額は657万円ですので、すべて控除の対象となり税金は発生しません。
関連記事
iDeCo(イデコ)とつみたてNISAの併用で資産を築く方法。30代共働きのベストチョイスは?
主婦がiDeCoを始めるデメリット・注意点

メリットが大きいiDeCoですが、その一方で「60歳まで引き出せない」「運用で損をするかも」といった不安の声も聞かれます。
iDeCoを始める前に、これらのデメリットや注意点をしっかり理解しておくことで、より賢明な判断ができるでしょう。主婦の視点で、特に押さえておきたいポイントを見ていきます。
60歳まで引き出せない
iDeCoの最大のデメリットは、原則として60歳になるまで引き出しできないことです。
例外として、障害により働けなくなった場合や死亡時、海外移住時には中途引き出しが認められますが、それ以外の理由(住宅購入や子どもの教育資金など)では引き出すことができません。
そのため、これらの支出に備えた別の資金計画も必要です。
今後出産や住宅購入などの出費を予定している場合は、60歳まで引き出せなくても問題ないか、慎重に判断する必要があります。
60歳まで引き出せないのが不安な場合は、同様の仕組みであるNISAを活用するのも1つの方法です。
NISAは所得控除などのメリットはありませんが、運用益については非課税になるため、収入の少ない主婦にとっては、iDeCoに近いメリットが得られる制度です。
運用期間中手数料がかかる
iDeCoのデメリットの2つ目は、手数料がかかることです。
iDeCoは加入時に支払う2,829円(税込)の加入時手数料、国民年金基金連合会と信託銀行に毎月支払う手数用171円(国民年金基金連合会に105円+信託銀行に66円)が発生します。
そのほか、加入する金融機関によって口座管理料が発生します。口座管理料は、0円から500円程度まであり、金融機関によって金額が変わるため、金融機関選びも重要です。
数百円でも毎月発生し、数十年の長い期間の運用となると高額になります。運用益以上に手数料のかかる手数料負けがないようにする必要があるでしょう。
運用リスクがある
iDeCoは預金と異なり、選んだ商品によっては元本割れのリスクがあります。投資信託や債券、不動産に投資するREITなどを選択できますが、それぞれ元本割れのリスクがあります。
市場動向により、投資期間や売買の時期によって資産が大きく増えることもあれば、値下がりすることもあります。
投資商品については、自分のリスク許容度(どこまで減っても耐えられるか)によって、選択する必要があります。絶対に資産を減らしたくない場合は、元本保証型の定期預金も選択できますが、手数料負けにならないように注意しましょう。
関連記事
無職になったらiDeCoはどうしたらいい?メリットと注意点をわかりやすく解説!
主婦がiDeCoを始める手順

「iDeCoを始めたい!」と決心したものの、「手続きが複雑そう…」「どの金融機関を選べばいいの?」という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、手順を理解すれば思ったより簡単に始められます。これから、主婦がiDeCoを始めるための具体的な手順とポイントを、順を追って解説していきます。
手順1.申し込み前の準備
iDeCo加入には以下の書類が必要です。
- 基礎年金番号がわかる年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 銀行口座の通帳(掛け金引き落とし用)
これらの書類をもとに、個人年金加入申込書や預金口座振替依頼書を記入し申し込む金融機関へ提出します。
手順2.金融機関を選ぶ
iDeCoは、現在預金を預けている金融機関でも取り扱える場合がありますが、口座管理手数料がかかったり、取り扱いできる金融商品が少なかったりします。
iDeCoを申し込む前に手数料や取り扱い商品を確認し、できるだけ手数料の安い証券会社を選択しましょう。ネット証券会社のほとんどが口座管理手数料は0円ですので、特に理由がなければネット証券で口座開設することをおすすめします。
おすすめの金融機関は以下となります。
- SBI証券
- 松井証券
- 楽天証券
どちらも口座管理料は無料、取り扱い商品の本数も多くさまざまな金融商品から選択できます。
手順3.実際に申し込む
申し込む証券会社が決まったら、以下の手順で申し込みを進めます。
- 金融機関のウェブサイトで仮申し込み
- 必要書類を揃えて本申し込み書類を郵送
- 国民年金基金連合会での審査(2-3週間)
- 加入承認書の受け取り
- 掛け金の引き落とし開始
一般的に、申し込みから実際の運用開始まで1-2ヶ月程度かかります。年末調整の効果を最大限活用するなら、早めの手続きがおすすめです。
手順4.投資商品を選択する
申し込みが完了したら、いよいよ投資商品を選択します。はじめての投資であれば、まずはリスクが低めのものから進めるとよいでしょう。
iDeCoでは分散投資と長期投資でリスクを抑えた運用ができます。分散投資は、1つの金融商品に限定して投資するのではなく、複数の商品に分散投資することで特定の値動きで資産が大きく目減りすることを防げるメリットがあります。
例えば、国内株式と海外株式に分散投資することで、日本国内の株価が下がっても、海外株式の価格が上昇すればトータルで利益を上げられます。
分散投資の組み合わせに不安がある場合は、バランス型の商品がおすすめです。これは証券会社でバランスよく投資商品を組み合わせていますのでこれ一つで分散投資ができる商品です。
また、さらにリスクを下げたい場合は、元本保証型の商品の比率を上げる、債券の比率を増やすなどの対応をするとよいでしょう。
長期投資は、複利の効果で資産の最大化を目指す投資方法です。運用で得た利益を再び投資することで、さらに利益を増やせます。
iDeCoの場合、60歳まで引き出せないため、一時的な株価の変動に動揺することなく長期的な目線で運用することを心がけましょう。
まとめ

専業主婦(主夫)は、所得税がかからない範囲で収入を得ている場合が多く、iDeCoで資産運用する場合の所得控除の恩恵を受けられないと考えている方も多くいると思います。しかし、主婦でも毎月積み立てし、運用益が出た場合については、運用益が非課税になるなどメリットが出せる制度です。
また、パートでも収入をさらに増やしたい場合については、所得控除のメリットを活かすこともできます。
デメリットとしては、60歳まで引き出せないという点があられますので、iDeCoの加入については、60歳まで引き落とす必要がない余裕資金で実施することが重要です。
資産運用をしたいが60歳まで引き出せないのがリスクと感じる場合は、NISAでの運用をおすすめします。
iDeCoでもNISAでも資産運用は分散投資と長期投資が重要です。自分のリスク許容度に応じた資産運用をすることが大切です。

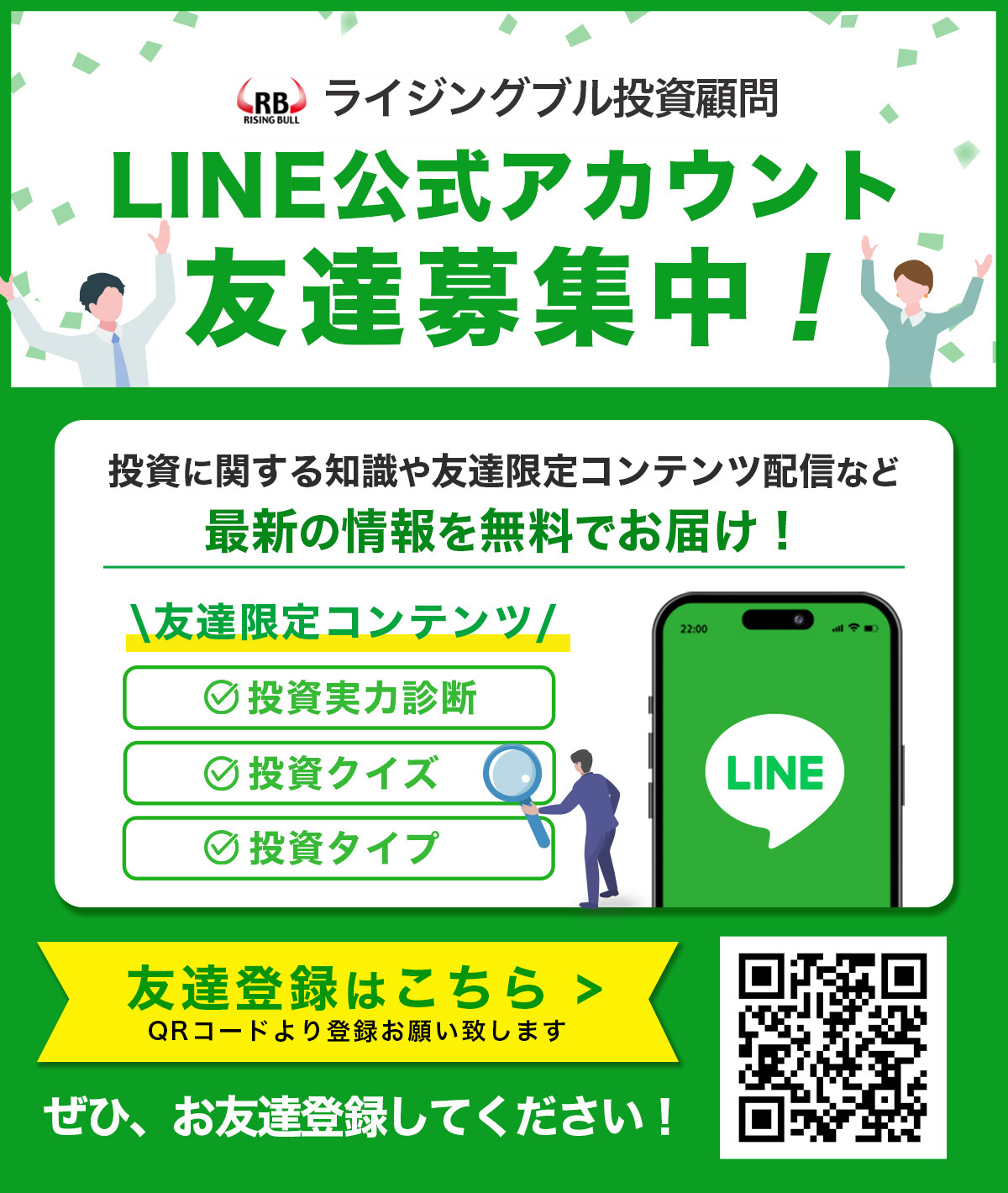
コメントComment