
2024年から始まる新NISAは、口座開設期間の恒久化や非課税保有期間の無期限化など、従来のNISAとは比べものにならないほど使い勝手が良くなります。
若い世代の資産形成から高齢世代の老後2,000万円問題まで、幅広く解決してくれる可能性がある魅力的な制度です。新NISAのポイントを押さえて、しっかり活用しましょう。
目次
現行のNISA

現行のNISAは、次の3種類から構成されます。
1.一般NISA
2.つみたてNISA
3.ジュニアNISA
それぞれの特徴をまとめると、次のようになります。
| NISA(20歳以上) | ジュニアNISA(20歳未満) | ||
| 一般NISA | つみたてNIISA | ||
| 制度開始 | 2014年1月~ | 2018年1月~ | 2016年4月~ |
| 非課税保有期間 | 5年間 | 20年間 | 5年間 ※ただし、2023年末以降に非課税期間が終了するものについては、20歳まで非課税で保有を継続可能。 |
| 年間非課税枠 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
| 投資可能商品 | 上場株式・ETF・公募株式投信・REIT等 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託※金融庁への届け出が必要 | 一般NISAと同じ |
| 買付方法 | 通常の買付け・積立投資 | 積立投資(累積投資契約に基づく買付け)のみ | 一般NISAと同じ |
| 払出し制限 | なし | なし | あり(18歳まで)※災害等やむを得ない場合には、非課税での払出し可能。 |
| 備考 | 一般とつみたてNISAは年単位で選択制2023年1月以降は18歳以上が利用可能 | 2023年末で終了 | |
引用:金融庁 NISAとは?
現行のNISAは2023年で終了します。一般NISAとつみたてNISAは選択制で、非課税保有期間は5年から20年です。非課税枠についての概略は次のとおりとなります。
1.一般NISA
非課税枠は、120万円を5年間で600万円まで
2.つみたてNISA
非課税枠は、40万円を20年間で800万円まで
つみたてNISAは、2023年中でも行えます。その後20年間運用可能です。
3.ジュニアNISA
非課税枠は、年間80万円を20歳まで運用可能
新NISAの特徴
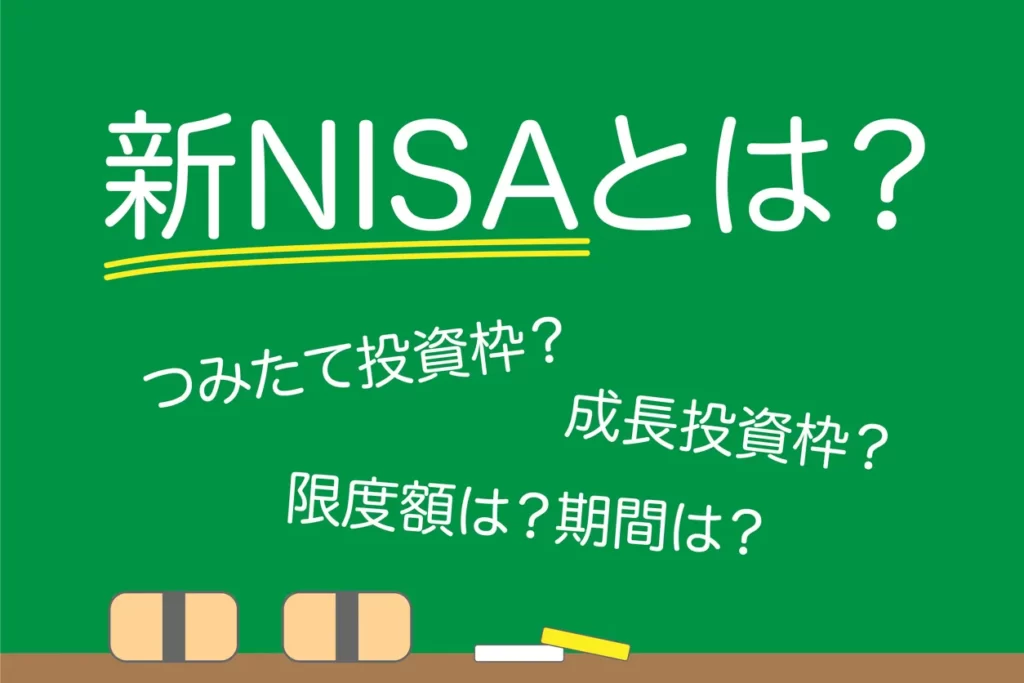
2024年から始まる新NISAでは、非課税口座の開設期間が恒久化され、非課税保有期間が無期限化されました。
年間投資枠も増額されており、2023年で原則終了する現行のNISAの内容と比べ、大幅な制度改善となります。新NISAのポイントは次のとおりです。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
| 年間投資枠 | 240万 | 120万 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 非課税保有限度額(総枠) | 全体で1800万円(内成長枠投資枠:1200万円) | |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
| 投資対象商品 | 上場株式・投資信託等 (①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリパティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外) | 長期の積立分散投資に適した一定の投資信託 (現行のつみたてNISA対象商品と同様) |
| 購入方法 | スポット・積立 | 積立 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
| 現行制度との関係 | 2023年末までに現行の一般NISAおよびつみたてNISA制度において投資した商品は、新しい制度の外枠で現行制度における非課税措置を適用 ※現行制度から新しいロールオーバーは不可 | |
引用:金融庁 NISAとは?
この章では、新NISAの特徴を順番に解説していきます。
1.年間投資枠の拡大
非課税で年間投資できる枠が拡大されました。
• つみたて投資枠:年間120万円
• 成長投資枠 :年間240万円
併用すれば、年間最大360万円まで投資可能です。現行NISAでは一般NISAの限度額が120万円であることを考えれば、年間投資枠は3倍に広がりました。
2.非課税保有期間の無期限化
現行のNISAでは、非課税期間はつみたてNISAの20年が最大でしたが、新NISAでは無期限となります。限度額内の投資であれば、一生非課税となるのが特徴です。
3.非課税保有限度額は全体で1,800万円
新NISAでは、生涯の非課税保有限度額が1,800万円となります。このうち成長投資枠の上限は1,200万円です。成長投資枠を使わなければ、すべての枠をつみたて投資枠に充てられます。
さらに、枠の再利用が可能であることもメリットです。新NISAを非課税限度額まで利用していても、一旦売却すればまた空きが出た分の活用が可能となります。
4.口座開設期間の恒久化
新NISAでは、口座の開設期間が恒久化されました。非課税口座を恒久的に保有し続けられます。頻繁な制度改正が行われないので、安心して投資を続けられます。
5.つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になりました。現行のNISAでは、選択制だったので、新NISAで投資する際に選べる金融商品の選択肢が増えます。
豊富な選択肢を利用することで、大幅に拡大される非課税枠を最大限に活用できるメリットがあります。
恒久化される新NISAでできること
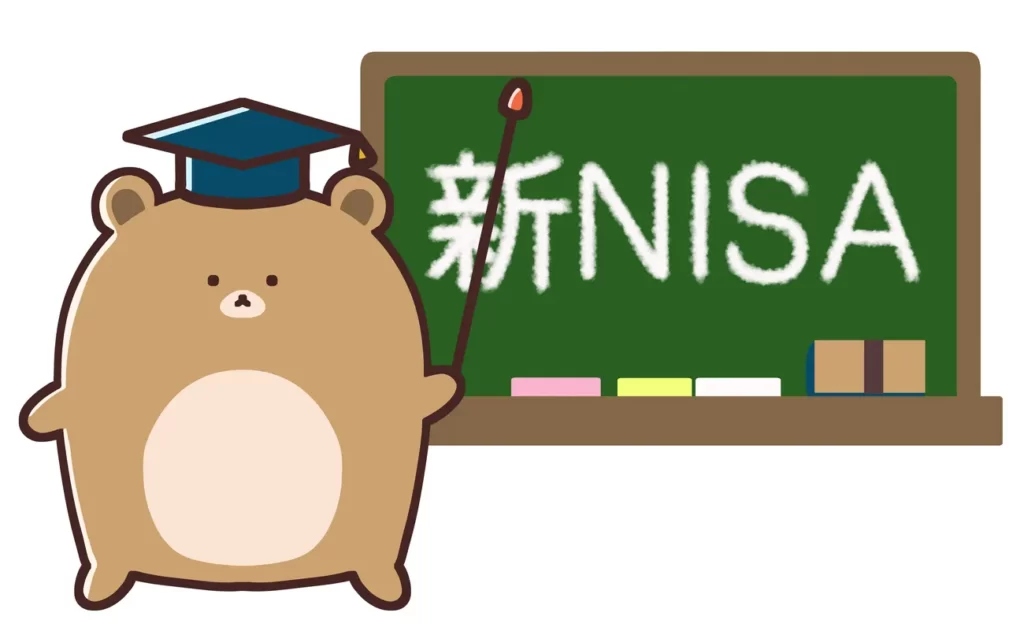
次に、恒久化される新NISAでできることを解説します。
1. 十分な老後資金の準備
新NISAは非課税保有限度額が1,800万円に拡大されたので、十分な老後資金を準備できます。例えば、25歳から55歳までの30年間に毎月5万円ずつ投資すると、元本だけで限度額の1,800万円です。
これを年率5%の利回りで運用できたとすると、運用益を合わせた積立金総額は約4,161万円と試算されます。(参考:金融庁 資産運用シミュレーション )
この試算は細かい運用条件や手数料などのコストを考慮していませんが、運用益を含めた全額が非課税となることを考慮すると大変魅力的です。
利回りを5%と仮置きした試算ではありますが、上下しても老後2,000万円問題を十分にクリアする結果となります。実際の運用ではシミュレーションどおりにはいかない場合もあるかもしれませんが、興味深い試算結果と言えます。
2.投資の自由度が拡大
新NISAでは非課税保有期間の無期限化や口座開設期間が恒久化に加え、つみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、投資の自由度が大幅に拡大します。非課税期間が生涯続くため、好きなタイミングで投資可能です。
また、早期に1,800万円満額を投資したり、毎月数万円ずつ積み立てしたりすることも可能で、投資する人の事情に合わせ、選択の幅が大きく広がり自由度が増すことになります。
新NISAの活用方法
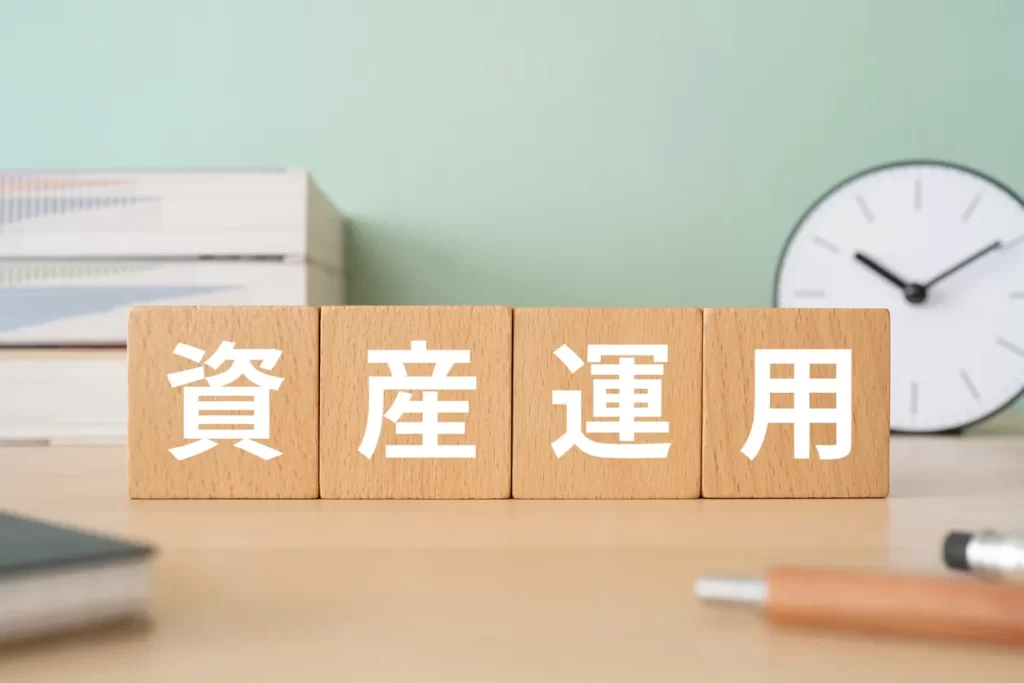
新NISAをうまく活用するためのポイントを解説しましょう。
1.長期投資を前提に
非課税期間が無期限化されたメリットを生かすには、長期保有で複利効果を期待する投資ができることです。例えば、株式市場は短期的には株価が上下することもありますが、数十年のスパンで見ると大きく値上がりしています。
また、長期投資はリスクを軽減する効果もあるので、安定した資産形成につながります。
2.つみたて投資枠と成長投資枠の併用
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能です。それぞれの非課税枠を合わせると、年間で360万円、生涯で1,800万円利用できるので、枠の大きさはこれまでのNISAとは比べものになりません。
また、つみたて投資枠と成長投資枠では、投資できる対象商品に特徴があります。
つみたて投資枠では、金融庁が積み立てに適すると認めた「長期のつみたて・投資に適した一定の投資信託」に投資可能です。一方、成長投資枠では、つみたて投資枠よりも対象の広い上場株式や一定の投資信託を選べます。
まずは、インデックスファンドを中心につみたて投資を行い、さらに投資できる余裕があれば、成長投資枠で株式やより高い利回りに期待できる投資信託に投資することも可能です。
これら2つを組み合わせれば、これまでより自由に自分の好みの金融商品をポートフォリオに組み入れられます。
3. コストの安価な金融商品を選択
新NISAは元本のみならず運用益も非課税ですが、維持管理コストが安価な金融商品を選択すればさらに効果を発揮します。投資信託の信託報酬は金融商品によって一律ではなく、特にインデックスファンドは低く設定されているのが特徴です。
信託報酬など割高な商品を選ぶと、長期投資でコストは大きく膨らむ可能性があります。コストを抑えることで、より多くのリターンを狙いましょう。
4. 口座開設する金融機関は慎重に
新NISAで開設できる口座は1人一口座だけである点は、従来のNISAと同様です。新NISAも証券会社や金融機関などで口座開設できますが、売買手数料や口座の維持管理に関する料金は同じではありません。
できるだけ口座の維持管理コストの低いところを選ぶと良いでしょう。ただし、コストが低いだけではなく、使い勝手の良い金融機関を選ぶことも大切です。
証券会社などの窓口に出向かなくてもパソコンやスマホから操作ができるのはもちろんのこと、分かりやすく簡単な操作性も大切です。いくつかの一般口座で操作性を試してから、自分に合った金融機関でNISA口座を開設すると良いでしょう。
関連記事→NISA口座変更の基本的な手順大公開!つみたてNISAは移管できる?
5. 少額から分散投資
新NISA制度は非課税で投資できる枠の大きさが魅力ではありますが、元本が保証されているわけではありません。投資する商品や運用方法によっては損失を被る可能性もあるため、投資に慣れていないうちはまず少額から運用を始めるのがおすすめです。損失を出しても生活に影響が出ない、余裕資金の範囲内でスタートしましょう。
新NISAの注意点

新NISAは投資をする人にとってメリットが多く、利用しない理由は見当たりません。それでも注意すべき点があるので解説します。
新NISAは損失が出ないわけではない
新NISAは非課税枠と期間が拡大されましたが、利用すれば必ず運用益が出るわけではありません。税制上の優遇措置があるのは大きなメリットですが、投資する金融商品によっては損失が発生する可能性があります。
NISAに限らず、どの金融商品でも必ずリスクがあります。自分の求める収益に対してどの程度リスクを許容できるか考えることが必要です。投資で運用できる資金を活用するのはよいですが、生活に必要な資金を無理に融通してNISAに充てることは止めましょう。
また、投資は長期的に行うことでメリットを生かせます。短期投資で株価が乱高下すると、投資家が安心できない場合があるでしょう。長期的に投資できる余裕資金がないと、少し株価が上下しただけで一喜一憂して、売買をくり返し損してしまう可能性もあります。
投資家の年齢によっても、NISAに投資できる金額は異なります。余裕資金の量や年齢など、投資できる環境と個人のリスク許容度によっては、新NISAでも損をする可能性もあることは覚えておきましょう。
現行NISAと新NISAは別のもの
現行NISAと新NISAは別の制度です。投資できる商品も非課税枠も同じではない点に注意が必要です。非課税口座も別に用意しなければなりません。
また、来年以降も一部残る現行NISA(つみたてNISAやジュニアNISA)の運用期間中に、新NISAを利用することもできます(来年度以降、現行NISAの新規投資は不可)。ただし、現行NISAで被った損失を新NISAの収益と通算するようなことはできません。あくまでも別の制度である点には注意しましょう。
現行NISAから新NISAへロールオーバーができない
現行NISAから新NISAへ引継ぎはできません。これまでは現行の一般NISAでは投資する年が終わると、次年度の非課税枠に自動的にロールオーバー(移管)させることができました。しかし、現行NISAと新NISAは別の制度であるため、現行NISAで運用していた資金をそのまま手続きせずに新NISAでも運用することはできません。
新NISAの口座を同じ金融機関で開設したい場合は、新しく資金を用意するか、現行NISAで運用していた金融商品を売却した後にNISA対象商品を再購入する必要があります。同じ金融機関を利用したい場合、ロールオーバーできない点に注意しましょう。
まとめ

2024年からのNISAは、年間の非課税投資枠が拡大するだけでなく、口座開設期間が恒久化や非課税保有期間の無期限化などメリットの大きな制度になります。長期で資産形成するには、大変魅力的な制度です。
また、現行NISAとは別の制度なので、新NISAに合わせて口座を準備する必要があります。なお、2023年中であれば現行NISAも利用できます。2024年からの制度開始に乗り遅れないように、新NISAを理解しておきましょう。


コメントComment