
一般的に株式よりも値動きが安定しており、ポートフォリオのリスク分散に活用される債券。
老後資金を確保するために、低リスクかつ好きなタイミングで売買できる「債券ETF」に挑戦したいと考える方もいるでしょう。
しかし、一部の投資家の間で「債券ETFはおすすめしない」という意見もあるため、初心者はどちらが正しいのか判断に迷うものです。
本記事では、債券ETFのメリット・デメリットを説明し、どんな人向けの投資先なのかを解説します。
債券ETFのおすすめ運用方法についても紹介しているので、ライフイベントや老後に向けて着実に資産を増やすための参考にしてみてください。
目次
債券ETFはおすすめしないと言われる5つの理由・デメリット

債券ETFがおすすめしないと言われる理由は、以下5つのデメリットがあるからです。
- 満期がないため元本が保証されない
- 株式や投資信託より狙えるリターンが少ない
- 流動性が低いとスプレッドが広がりやすい|売買手数料の高騰
- 金利上昇時に価格が大きく下落しやすい|デュレーションリスク
- リターンが物価上昇に追いつけない可能性がある|インフレリスク
上記を理解せずに投資すると、思ったより利益を出せずに、老後資金を十分に確保できない可能性があります。
満期がないため元本が保証されない
本来の債券には、満期時に債券を買ったときの金額(額面金額)が戻る「償還期限※」が設定されています。※額面どおりの金額が返済される最終日
しかし、債券ETFは市場で常に売買されるために償還期限がなく、満期を待っても元本を回収できません。
金利の上昇で債券価格が下落すると、売却時に損失が生じる可能性があります。「保有していれば元本が返ってくる」とは限らない点は、個別債券との大きな違いです。
株式や投資信託より狙えるリターンが少ない
債券ETFは、株式や投資信託と比べて狙えるリターンが少ない傾向にあります。
債券自体が「安全性」を優先した商品であり、値上がり益や利息(クーポン)による高利回りを狙いにくいからです。
たとえば、投資信託の長期運用なら3〜10%の利回りを期待できますが、債券ETFの利回りは1〜2%程度にとどまるケースもあります。
資産を大きく増やしたい人にとって、債券ETFは物足りなさを感じるでしょう。
流動性が低いとスプレッドが広がりやすい|売買手数料の高騰
債券ETFの取引量が少ないと、スプレッド(売値と買値の差)が広がりやすいです。スプレッドが広いと実質的な売買コストが上がり、利益を削ってしまいます。
とくに、新興国債券を組み入れたETFは売買が成立しにくく、スプレッドが広い傾向にあります。
投資信託と比べると全体的に取引量が少ないため、債券ETFでは流動性リスクを避けにくいでしょう。
金利上昇時に価格が大きく下落しやすい|デュレーションリスク
デュレーションとは、金利が変わったときに債券価格がどれだけ動くかを示す指標です。
「金利が上がると債券価格が下がる」という仕組みは債券ETFも同様であり、金利変動リスクを避けられません。
たとえば、デュレーション5年の債券ETFに100万円投資した場合、金利が1%上がったときの最終金額は約95万円※です。
※計算式:金利1%×5年=約5%の下落
とくに、デュレーションが長いETF(20年や30年などの長期国債を組み入れた商品)ほど、金利上昇時の値下がり幅が大きくなるリスクがあります。
リターンが物価上昇に追いつけない可能性がある|インフレリスク
物価が上昇(インフレ)すると、同じ利回りでも「実質的な利益」は減少します。
債券は利回りが低めなので、インフレによる物価上昇スピードに追いつかない可能性があるからです。
たとえば、100万円投資して年1万円(1%)の利益が出ても、物価が2%上がれば実質1万円のマイナスとなります。
インフレが進む段階において、債券ETFは「利息があっても実質利益は減る」ことを理解したうえで投資を検討しましょう。
債券ETFとは|複数の債券を組み合わせた上場投資信託

債券ETFとは、複数の債券をパッケージにして、株式と同じように証券取引所で売買できる「上場投資信託」です。
個別に債券を購入するよりも手軽に分散投資ができ、比較的リスクを抑えて債券投資に挑戦できます。また、市場が空いている時間帯ならリアルタイムで売買できるので、現金化しやすいのも魅力です。
債券ETFのおもな種類として、以下が挙げられます。
- 国内債券ETF:日本国債や日本企業の社債に投資
- 海外債券ETF:海外の国や企業の債券に投資
- 米国債ETF:米国インデックスへの連動を目指す債券に投資
- 新興国債券ETF:ハイリスクハイリターンな新興国の債券に投資
- ハイイールド債券ETF:信用格付が低いために利回りの高い債券に投資
株式より値動きが少ない傾向にあるため、債券ETFは安定性を重視する投資家に適した商品です。
債券ETFの6つのメリット

債券ETFへの投資には、以下6つのメリットがあります。
- 少額から分散投資を始められる
- リアルタイム売買で現金化しやすい
- 株式投資より安定的にリターンが狙える
- 専門知識なしでも債券投資に挑戦できる
- 満期がないので長期運用でも利益を狙える
- 個別債券より銘柄選びや購入時の手間が少ない
安定性を重視したい方には、債券ETFが有力な選択肢となるでしょう。
少額から分散投資を始められる
債券ETFは、少額からでも複数の債券に分散投資できます。本来、個別債券は1口単位での取引となるため、数万〜数十万円単位での購入が一般的です。
一方で債券ETFなら、ネット証券を通じて数千円程度から購入できる商品もあります。
投資初心者でも小さな金額から始められるため、低リスクで債券投資に挑戦できるのが債券ETFの魅力です。
リアルタイム売買で現金化しやすい
債券ETFは、株式と同じように取引所でリアルタイム売買が可能です。
市場が動いている時間帯ならいつでも現金化できるので、ライフイベントやポートフォリオ調整などで現金が必要なときでもすぐに対応できます。
必要な分だけ売却できる柔軟性も、債券にはない「債券ETF」ならではのメリットです。
株式投資より安定的にリターンが狙える
債券ETFを運用すれば、株式投資より安定したリターンが期待できます。
債券は定期的に利息を生み出す仕組みがあり、景気や企業業績による値動きが大きい株式に比べて、価格の変動が小さいからです。
とくに、市場が不安定なときでも一定収益を確保しやすいので、債券ETFは老後資金を目的とした投資に向いています。
専門知識なしでも債券投資に挑戦できる
個別債券に投資する場合、ポートフォリオ内の複数銘柄のバランス調整を自分で行う必要があります。
一方で、債券ETFは専門家が自動的にリバランス(組み換え)してくれるので、専門知識のない初心者でも債券投資に挑戦しやすいです。
市場環境の変化に応じた運用調整もプロに任せられるため、個別債券より投資ハードルが低いと言えます。
満期がないので長期運用でも利益を狙える
債券ETFには満期がありません。
自分で売買タイミングを決められるため、利息と値上がり益を狙った長期運用も可能です。
とくに、インデックス型の債券ETFを持ち続ければ、分配金を受け取りながら価格上昇による利益も期待できます。
老後資金を目的とした投資先として、安定的に運用し続けられる債券ETFは選択肢のひとつとなるでしょう。
個別債券より銘柄選びや購入時の手間が少ない
個別債券に投資する場合、国や企業ごとに「倒産リスク」や「デュレーションリスク」などを細かく分析する必要があります。
一方で、債券ETFは「専門家が複数の債券を組み入れて運用する商品」であり、購入する銘柄選びの手間がかかりにくいです。
1つのETFを買うだけで数十〜数百の債券に分散投資できるため、初心者でも債券投資に挑戦できます。
債券ETFが向いている人・向いていない人
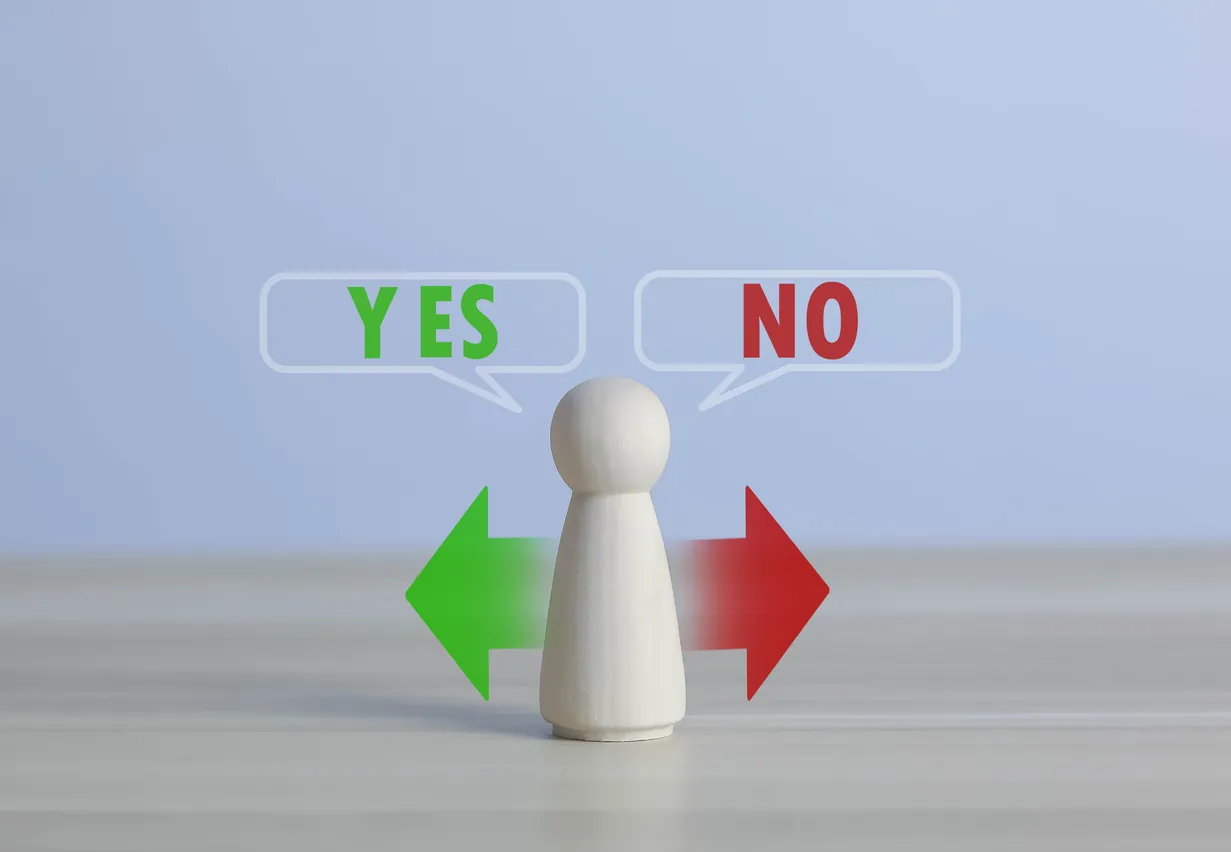
債券ETFが向いている人・向いていない人の特徴を、下表にまとめました。
| 向いている人 | 向いていない人 |
| ・少額で債券投資に挑戦したい人 ・分散投資でリスクを抑えたい人 ・株より安定的に利益を狙いたい人 ・定期的に分配金で収入を得たい人 ・長期的な資産形成を目指している人 | ・短期間で高いリターンを求めている人 ・償還期限による元本確保を重視したい人 ・決まった利回りを確実に受け取りたい人 ・今後、インフレが加速すると考えている人 |
とくに、短期的なリターンを狙っている方にとって、債券ETFの利回りの低さは物足りなさを感じるでしょう。
また、将来的にインフレが加速すると考えている方は、債券より株式投資の方が向いています。それでも、債券ETFは株式投資より安定性に優れた投資先です。
長期運用で老後資金を確保するのに向いているので、自分の投資目的に合っていれば少額で挑戦してみてください。
債券ETFのおすすめ運用方法3つ

債券ETFのおすすめ運用方法を3つ紹介します。
- ポートフォリオの一部として債券ETFを組み込む
- 老後に近づくほど債券ETFの割合を増やしていく
- 長期の積立投資で平均単価を下げる|ドルコスト平均法
安定的なリターンを狙うための参考にしてみてください。
ポートフォリオの一部として債券ETFを組み込む
債券ETFと株式を組み合わせると、安定性の高いポートフォリオを作れます。
債券と株式はそれぞれ値動きが異なるため、リスク分散効果が高まるからです。
たとえば、株価が30%下落したときに債券ETFで20%の利益が出ていれば、ポートフォリオ全体の下落幅を10%に抑えられます。
実際に「株式60%・債券40%」のバランス型ポートフォリオは、世界的にも有名な組み合わせです。
リスクとリターンのバランスを調整したいときは、債券ETFを少額ずつポートフォリオに加えてみてください。
老後に近づくほど債券ETFの割合を増やしていく
年齢を重ねるごとに債券ETFへの投資割合を高めると、退職して老後を迎えたときに生活費を確保しやすいです。
まだ20〜30代なら株式投資でリスクを取れますが、40〜50代になると老後資金を増やすより「減らさない」ことが最優先となります。
40代なら40%程度、50代なら50%以上を債券ETFに投資するなど、年齢に応じて債券ETFの比率を調整すれば、老後資金を取り崩す際の不安が減るでしょう。
長期の積立投資で平均単価を下げる|ドルコスト平均法
ドルコスト平均法とは、毎月一定額の積立を長期的に続ける投資手法です。
価格が高いときには少なく、安いときには多く購入できるため、投資期間全体の「平均購入単価」が下がります。
優良な債券ETFを長期的に積み立てれば、価格変動リスクを抑えながら、安定して老後資金を準備できるでしょう。
まとめ

老後資金を確保するための安定的な投資先として、リスクを分散できる債券ETFは魅力的な選択肢です。
しかし、元本が補償されない点やリターンの低さ、インフレに弱いなどのデメリットもあります。
「債券なら安全」と思い込んで投資すると、思ったより利益が出なかったり、値下がりで損失が生じたりと、期待はずれの結果になりかねません。
それでも、債券ETFをポートフォリオの一部として取り入れたり、老後が近づいたら比率を増やしたりするなど、使い方次第でリスクを抑えた運用が可能です。
債券ETFの特徴を正しく理解し、自身のライフステージや投資目的に合っているのかを十分に検討したうえで、投資に挑戦してみてください。


コメントComment